小学生になったばかりの子どもとの毎日、
楽しいけどちょっとドキドキする場面も増えてきませんか?
「急に友達がピンポンしてきた」
「勝手におうちに入ってしまった」
など、小1ならではの“遊びトラブル”は意外と多いんです。
先輩ママたちから聞いた様々なトラブル・・・
親同士解決できたらいいけどそうじゃない場合ももちろんある!
ということで、トラブル回避のための、
おうちの約束(親→子Ver.)を教えます。
▼このシリーズでは、小学生になったばかりの子どもたちが安心して遊べるように、家庭内・友達同士・親同士で決めておきたい「遊びの約束」をまとめています。
ぜひ、あわせてチェックしてみてくださいね。
この記事では、小学生との毎日を安心して過ごすために我が家で話し合った
「おうちの約束」10選を紹介します。
ルールは、子どもをしばるためのものではなく“安心して遊べるための味方”。
子どももママも笑顔になれる工夫、ぜひ参考にしてみてくださいね。
我が家で決めたおうちの約束10個
子どもが小学生になりました。
我が家では「おうちで守る約束」を家族会議で決めました。
きっかけは、ある日の放課後。私は不在、夫が在宅勤務の時でした。
突然同じクラスの子が訪ねてきたのです。
息子はその時ピンポンが鳴ったことに気が付かず、
夫も在宅勤務別室に居たのでピンポンの音が聞こえなかったようです。
(我が家は1歳の赤ちゃんがいるのでピンポンの音は最小にしてあります)
その日の夕方、またピンポンが鳴りました。
今度は息子も気づいていて、「友達が遊びに来た」と夫に報告。
時計を見ると午後5時。
「もう帰ってもらいなさい。」と夫はインターホンを観ずに子どもに伝えます。
子どもは出方もわからないのでそのまま・・・・・・・・
ということがありました。
それを聞いた私はびっくり!すぐにインターホンを確認!(録画)
インターホンを見てみると、5時のインターホンには子どもとママの姿。
・子どもは訪ねてきた友達の名前は知らないけど同じクラス
・どこに住んでいるのかは知らない。

きっととご挨拶に来て下さったんだろうな。
その出来事をきっかけに、
「これは家庭内でもちゃんとルールを決めておかないと、
子ども同士・親同士、どこかで迷惑をかけてしまうな」と感じたんです。
でも、小1の子どもにいきなり「ルールを作るよ!」って言っても、きっとピンとこないですよね。
そこで、わが家では子どもと一緒に“話し合う”スタイルにしました。
「○○ちゃんが急に来たとき、どう思った?」
「おうちに誰もいなかったら、どんな気持ちになるかな?」
そんなふうに、子ども自身に“考えてもらう”スタートを切ったんです。
そのうえで、「じゃあ、どうしたらみんなが気持ちよく遊べるかな?」と問いかけながら、
次のような10個の“おうちの約束”が出来上がりました。
おうちのお約束(親→子Ver)
| おうちの約束 |
|---|
| 1. お友達が来たら、まず大人に伝える |
| 2. 勝手におうちに入れない |
| 3. チャイムは1回でOK、出なかったらまた今度 |
| 4. 夕方○時までに帰る(わが家は17時)冬はもう少し早める予定 |
| 5. 誰とどこで遊ぶか、行く前に教える |
| 6. 断られたら怒らない |
| 7. 断る勇気を持つ |
| 8. おやつは勝手にあげない、もらわない。自分の分のおやつと水を持っていく。 |
| 9. 宿題を終わらせてから遊ぶ |
| 10. おうちの人にありがとうを伝える |
どれもすごく基本的なことなんですが、子どもにとっては初めて「自分で行動する」タイミング。
「○○ちゃんにありがとう言った?」って聞くと、
「あ、忘れてた!」と気づいてくれるし、
断る練習をしておくと、無理に付き合って疲れることも減ります。
特に意識したのは、「お友達を巻き込まないこと」。
子どもって、悪気なく「今日うちで遊んでいいってママが言ってた」とか言っちゃうんですよね。
でも、親としては「いやいや、聞いてないし!」ってことが多々あります。
だから、
うちでは「ママに聞いてからにしようね」
「大人にOKって言われてから、約束しようね」というルールにしました。
あと、よくあるのが“チャイム問題”。
これはご家庭によっても違うと思いますが、
我が家では
「1回押したら待ってみる」
「出なかったらまた今度」というふうにしています。
「何回もピンポンするのはびっくりするから、1回で大丈夫だよ」
って伝えると、子どもなりに納得してくれました。
こうしたルールは、
決して子どもを縛るためのものではなくて、
「みんなが気持ちよく過ごすための共通認識」なんですよね。
それをちゃんと説明してあげると、子どもも意外とすんなり受け入れてくれます。
ちなみに、うちではこの約束をA4の紙に書いて、リビングの壁に貼っています。
何度も言ったでしょ!とならずに、
「お約束確認しよう」といえば自然と約束を読んでくれるようになりました。
そしてポイントは、“完璧を求めないこと”。
最初からすべて守れるわけじゃなくて、
忘れたり、失敗したりしながら少しずつ身についていくものです。
できた日はしっかり褒めて、
「ありがとうって言えたね」「帰る時間、ちゃんと守れたね」と声をかけるようにしています。
こうした“積み重ね”が、子どもにとっての「安心」や「自信」につながっていくと感じています。
もし、あなたのご家庭でも「そろそろルールを決めようかな」と思っていたら、
ぜひこのリストを参考にして、わが家流の“おうちの約束”を作ってみてくださいね。
ルールを伝えるときのコツ
小1って、まだまだ「言葉のニュアンス」がむずかしい時期なんですよね。
だから、ルールを伝えるときには、できるだけ「やさしい言葉」を使うことが大切です。
●●したらダメ!という禁止行為を教えるのではなくて
やってほしいことを具体的に教えるのがポイントです。
脳は否定語を理解することができませんからね。
たとえば「勝手に入っちゃダメ!」ではなく、
「お友達が来たら、ママに教えてくれると嬉しいな」って伝えると、
素直に受け取ってくれることが多いです。
もうひとつのポイントは、“こうしようね”という前向きな言い方をすること。
「ダメ」を連発するより、「こうしたらいいよ」の方が、子どもは理解しやすいんですよね。
あとは、表やカードにして、目に見える形で置いておくのもおすすめ!
習いごとの時間割表みたいに、ちょっと可愛くしてあげると子どもも嬉しそうに見てくれます。
親も完璧じゃなくていいから、
まずは一緒に「どうしたら気持ちよく過ごせるかな?」
って考えてみるところから始めてみてくださいね。
詳しく読みたい①~⑩お約束のポイント
① お友達が来たら、まず大人に伝える
知らない子がいきなり家に入ってきたら、どんなママでもドキッとしますよね。
まず「◯◯くんが来たよ!」と教えてもらえるだけで、大人も心の準備ができます。
できれば帰ってきたときに報告してくれるように伝えると尚◎💮
💡 伝える=安心の第一歩。
子どもに「報告は信用のカギだよ」と優しく教えています。
② 勝手におうちに入れない
お友達が「入っていい?」と聞く前に勝手に家に入ってしまうと、家庭によってはトラブルに。
わが家では「家の中は家族の大切な空間」と伝え、「入れていいか、大人に聞いてから」と約束しました。原則は外で遊んでほしいけど物騒な昨今そうも言えない事情が悲しい。
💡「家のルールはそれぞれ違う」ということも、ここで学んでほしいなと思っています。
③ チャイムは1回でOK。出なかったらまた今度
連打チャイムやインターホン越しの「いる?ねぇー!」が迷惑になることも。
だから、「1回鳴らしたら、それでおしまい。出なかったらまた明日ね」と伝えています。
💡これで相手の家族への配慮も自然と身につきます。
④ 夕方○時までに帰る(我が家は17時)
「暗くなってきたから帰りなさい」と言われる前に帰ってくる習慣を。
季節によって時間も変え、「冬は16:30にしようね」と調整する予定です。
夕方のチャイムで帰る、これ私が子どもの頃からやっていましたね。
💡ルール化することで、子ども自身も安心して遊べます。
⑤ 誰とどこで遊ぶか、行く前に教える
これは防犯上とても大事です。
「どこで、誰と、なにをするか」を聞いておけば、何かあったときも対応できます。
問題は集合場所から移動した時。今はマンションの下の公園でのみ遊ぶことを許可しています。
💡「言いたくない場所」なら行かない勇気も、少しずつ教えていきたいところです。
⑥ 断られたら怒らない
「遊ぼう!」と声をかけて断られるのは、子どもにとって悲しいこと。
でもその時「なんで?」「いいじゃん!」と責めてしまうと、お友達との関係にヒビが入ってしまいます。
💡「相手にも予定があるんだよ」「また今度遊べるといいね」と声をかけています。
⑦ 断る勇気を持つ
「今日は気分じゃないな」「宿題がまだなんだ」「ごめんね今日は遊べないんだ」
気の乗らない誘いに「やだ」と言えず遊び続けてしまう子も多いです。
断る勇気は大切と思っています。
💡自分の気持ちを大切にしていいよ、と繰り返し伝えています。
⑧ おやつは勝手にあげない、もらわない。自分の分を持っていこう
アレルギーや家庭のルールの違いがあるおやつ問題。
そこで「おやつと水は自分の分を持参」「もらったら断る」をルールにしました。
クレクレくんにならないように今から教育。
もしもらってしまったら「ありがとう」を必ず言うことを伝えます。
💡これは親同士の信頼にもつながります。
⑨ 宿題を終わらせてから遊ぶ
生活習慣を作る上で大事なルール。
「宿題→遊び」の順番が自然になれば、自己管理力も育ちます。
まだまだ時間の間隔が身につかない小学校低学年。少しずつできるように練習中です。
💡「終わってからの方が、安心して遊べるよね」と前向きな声かけをしています。
⑩ おうちの人にありがとうを伝える
送り出してくれる家族にも、遊びに来てくれたお友達の家族にも。
感謝を伝えられる子に育ってほしいという願いから、この約束を最後に入れました。
ありがとうは本当に魔法の言葉。感謝を忘れない子どもであってほしいと願っています。
💡毎日の「ありがとう」が、子どもの人間関係を明るくします。
まとめ|小学生との「おうちの約束」は親子の安心材料
小学校に入ると、子ども同士のつながりがぐっと広がります。
でも、まだまだ“ルール”や“マナー”を知らない中でのやり取りは、トラブルの元になりがち。
だからこそ、家庭内で「我が家の約束」をしっかり決めておくことで、
子どもも自信を持って遊べるようになります。
ルールはガミガミ言うためのものじゃなくて、安心して過ごすための「お守り」みたいなもの。
家族で話し合って、ぜひ“わが家らしいルール”を作ってみてくださいね。
▼このシリーズでは、小学生になったばかりの子どもたちが安心して遊べるように、家庭内・友達同士・親同士で決めておきたい「遊びの約束」をまとめています。
ぜひ、あわせてチェックしてみてくださいね。
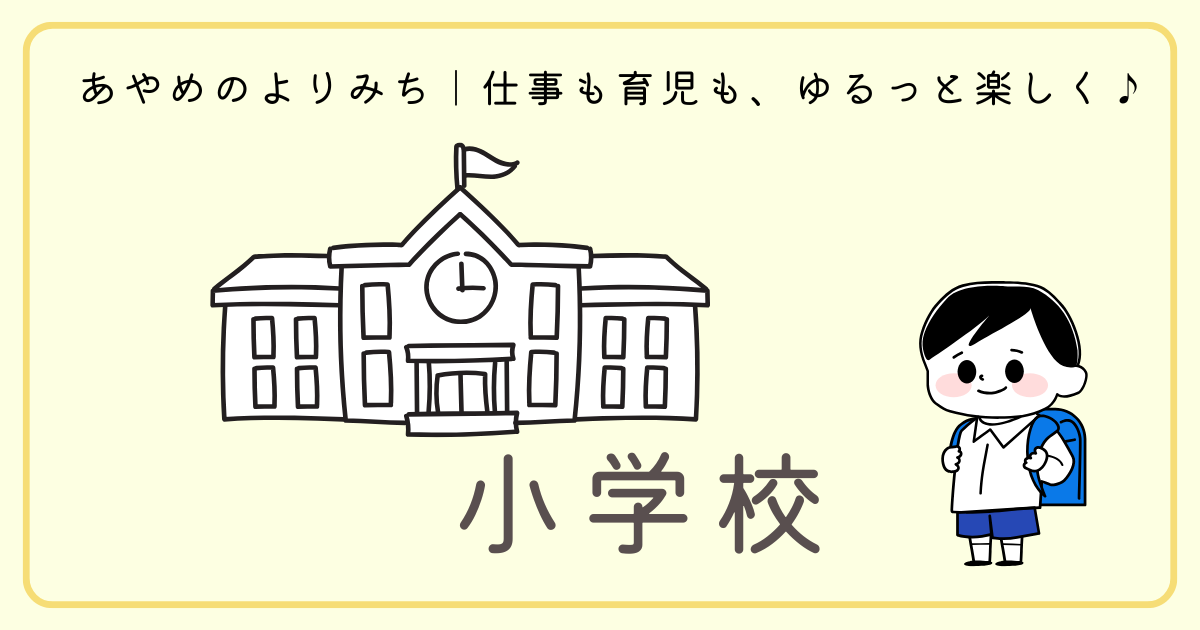

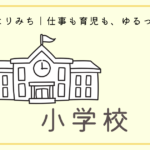
コメント