小学生の子どもの心と体の体調管理って、どうしていますか?
毎日の手洗いうがいから、病気への備え、さらには心の安定まで、
親として不安なことはたくさんありますよね。
この記事では、
小学生の子どもが健康に過ごすために大切な習慣や、病気になったときの対応、
そしてメンタルケアのポイントまで、幅広くわかりやすく解説します。
「ちゃんと健康でいてほしい」そんな思いに応えるための内容になっています。
読み終える頃には、毎日できる体調管理のヒントがきっと見つかるはずです。
ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
小学生の子どもの体調管理に欠かせない基本5つ
小学生の子どもの体調管理に欠かせない基本5つについて解説します。
それでは順番に、詳しく見ていきましょう!
①手洗い・うがいを習慣化する
体調管理の基本中の基本といえば、やっぱり「手洗い・うがい」ですよね。
特に小学生って、学校や外でたくさんの人と接するので
風邪やインフルエンザにかかるリスクも高いです。
「帰ったら手を洗う」「ごはんの前には手を洗う」「帰ってきたらうがいをする」
――これを毎日のルーティンにしてしまうのがコツです。
保育園・幼稚園から行っている人も多いのではないでしょうか。
ちなみに、手洗いは「ハッピーバースデー」の歌を2回分ぐらいかけて、
しっかり洗うとバッチリです!
正しい手洗いの方法は以下をご確認ください。

引用:正しい手洗いの方法(衛生学的手洗いのイラスト)看護roo!
子どもが面倒くさがることもあるけど、最初は一緒にやって楽しく習慣づけていきましょう。
特に疲れていると手を水で濡らして終わり!としがち。(我が息子もです)
なので、石鹸で洗ったか、時々手の匂いを嗅いでチェックしています。
②規則正しい生活リズムを作る
生活リズムがガタガタだと、体調だけじゃなくて、心のバランスも崩れやすくなります。
朝起きる時間、寝る時間、食事の時間――
これを毎日だいたい同じにそろえること(生活リズム)が、健康の土台作りの一歩です。
特に大事なのは「朝日を浴びること」。
太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされて、
自然と夜眠くなって、朝すっきり目覚められるようになります。
朝起きてカーテンを開けて太陽の光のパワーをエネルギーチャージしてくださいね!
またゲームやスマホの夜更かしには要注意。
家族全員で「夜はリラックスタイム」と決め、
寝る3時間前までにスクリーンタイムは終わりにするよう心がけましょう。
③栄養バランスの取れた食事を意識する
「好きなものばっかり食べてる!」ってこと、ありませんか?
でも小学生の体は、今ものすごい勢いで成長しているので、栄養バランスは本当に大事なんです。
主食(ごはん・パン)、主菜(お肉・お魚)、副菜(野菜・きのこ類)、汁物(みそ汁やスープ)、果物――こういう形で「バランスよく」揃えるのが理想です。
苦手な野菜がある子には、カレーやスープにこっそり入れる作戦もアリですよ!
無理に押し付けず、「美味しいね~」って一緒に楽しむのがポイントですね♪
どうやら乳歯から永久歯に歯が生え変わっているタイミングなので、
歯がぐらぐらするのが嫌みたいです。
塊の肉ではなくひき肉や細かく切った肉や魚など食べやすさを工夫して食べさせています。
植物性タンパク質より動物性タンパク質の摂取量が少ないのでまだまだ工夫が必要…。
④適度な運動で免疫力アップ
最近、運動不足の小学生が増えてるってニュース、よく見かけますよね。
令和5年度の文部化科学省の調査ではコロナ以前とコロナ後で体力合計点の差があるそうです。
(体力合計点・・・シャトルランや反復横跳びなどの競技点数。運動測定でやりましたよね!)
でも、外遊びや運動って、単なる体力作りだけじゃないんです。
毎日外で思いっきり遊ぶのが理想だけど、難しいときは「家の中でラジオ体操」でもOK!
楽しく体を動かすことが一番なので、「一緒にダンスしよう!」みたいに誘ってみてください。
⑤十分な睡眠時間を確保する
睡眠って、成長期の小学生には本当に大事なんです!
寝てる間に成長ホルモンが出て体や心の成長が促されると同時に回復するし、
心の疲れもリセットされます。
小学生の理想の睡眠時間は、だいたい9~11時間ぐらいと言われてます。
だから、朝7時前後に起きるなら、夜8時~10時には布団に入って寝られると良いですね。
寝る前はスマホやゲームはお休みして、
絵本を読んだり、静かな音楽を聴いたりして、自然に眠りにつける環境を整えてあげましょう。
小学生の病気予防で親ができるサポート4つ
小学生の病気予防で親ができるサポート4つについて解説します。
親として、子どもを病気から守るためにできることって、実は日々の積み重ね。
①感染症対策を日常に取り入れる
インフルエンザ、ノロウイルス、風邪、最近だとコロナ…。
小学校って、ほんとに感染症の温床になりやすいんです。
だからこそ、家庭でも「感染症対策の意識」を持つことが大切です。
具体的には、「外から帰ったら手洗い・うがい」「人混みではマスク着用」「タオルは家族で共用しない」など、ちょっとしたことの積み重ねが効果を発揮します。
アルコールスプレーや除菌グッズを玄関に置いておくのもおすすめです。
保育園幼稚園ではとにかく裸足なら足を洗うように!と書いていましたが
小学生になると上履きを履くので感染症対策として足を洗う必要はありません。
ただし、手や顔についたものが体内に入るのは避けたいので、
帰ってきたら手を洗うことに加えて顔を洗うと尚良いでしょう。
タオルの共用・共有と残り物を食べるのはやめてくださいね!
PR②予防接種をしっかり受ける
予防接種って、正直「面倒だな〜」「スケジュール調整大変」って思うことありませんか?
でも、これって病気にかかるリスクを大きく下げてくれる、すごく大事なサポートなんです。
小学生が受けるべき予防接種って、年齢ごとにスケジュールが決まってるので、母子手帳やお知らせをしっかりチェックすることが大事。
インフルエンザや新型コロナワクチンは、毎年流行状況に合わせて受けることが基本になります。
一方で、日本脳炎のように「決まった年齢で接種する定期予防接種」もあります。
たとえば初回は3歳ごろ、その後7歳半までに追加接種を受ける必要があります。
母子手帳や自治体からの案内で時期を逃さないようにチェックしておくと安心ですよ~!
病気になってからでは遅いので、カレンダーやスマホでスケジュール管理しておくのもおすすめです。
③早期発見・早期対応を意識する
「あれ、ちょっと熱っぽいかも?」って時に、「様子見」で済ませちゃうこと、ありますよね。
子どもの体って、大人よりも変化が早いので、早めに気づいて対応することがとても大事なんです。
たとえば、発熱や咳だけじゃなくて、
「いつもより元気がない」「食欲が落ちてる」「顔色が悪い」など、
ちょっとした変化にも目を向けてみてください。
子どもは自分の体調をうまく言葉にできないことも多いので、
日ごろの様子をよく見ておくことがポイントです。
「なんとなく変だな」と感じたら、早めに休ませたり、
かかりつけ医に相談するだけでも安心につながります!
小学生になったからと言って急にできることが増えるわけではないので、
幼稚園・保育園時代と同様、しっかり体調をチェックすることが大切ですね!
④体調チェックを習慣にする
朝の登校前、「元気?」って聞くだけになってませんか?
そのひと言ももちろん大事だけど、もう一歩踏み込んで、
「体調チェック」を習慣にするとグッと安心感が増します。
たとえば、
「朝の体温を測る」「顔色や言動、行動の変化を見る」「朝食がちゃんと食べられたか」などを
チェックすると良いです。
こうした観察から、「ちょっと様子がおかしいな」と気づけるきっかけにもなります。
また、子ども自身にも「今日はちょっとだるいかも…」と気づかせる習慣が身につきます。
毎日ほんの2〜3分でできることだから、ぜひルーティンにしてみてくださいね!
小学生の心の体調管理で意識したいこと5つ
小学生の心の体調管理で意識したいこと5つについて解説します。
体調管理というと、どうしても「体」のことに目がいきがちですが、
子どもの「心」も同じくらい大切です。
特に小学生は、環境の変化や人間関係のストレスを感じやすい時期。
心が不安定になると、体調にも影響が出ることがあるので、
日ごろから心のケアも意識していきましょう。
①話をじっくり聞く時間を作る
子どもとの会話、つい「聞いてるフリ」になってませんか?
実は、「話をちゃんと聞いてもらえている」という感覚は、
子どもの安心感や信頼感に直結するんですよ。
特に学校であったこと、友達との関係、楽しかったこと、嫌だったこと
――これを自分の言葉で話すことで、子どもは心を整理しています。
だから、家ではスマホやテレビをオフにして、
「あなたの話をちゃんと聞くよ」という姿勢を見せてあげるだけで、
気持ちがすごく安定するんです。
毎日5分でもOK。ゆっくり聞いてあげてください。
②自己肯定感を育てる声かけ
「あなたならできるよ」「頑張ったね」「ありがとう」
――たったひと言で、子どもは自信を持てるようになります。
小学生の時期って、勉強や運動、友人関係などで「自分はダメかも…」って感じやすいんですよ。
だからこそ、
家では「できたこと」に目を向けて、褒めたり認めたりすることがとっても大切なんです。
たとえば、漢字のテストで80点だったとき、「あと20点!」ではなく「よくここまで頑張ったね!」と声をかけてみてください。
そうすることで、子どもは「また頑張ってみよう」と思えるようになりますよ~!
できれば結果ではなく過程を褒めてください。
結果だけを褒めると、「成功しないと価値がない」と思いやすくなり、失敗を恐れて挑戦しなくなります。
正解を求めすぎると創造力や試行錯誤の力が育ちにくくなり、自発的な学びも減ります。
成果が出ないと努力が無意味に感じられ、継続する力や成長の意欲が低下することがあるので
結果にこだわらず過程を褒めるほうが良いです。
もちろん、良い結果が出たら結果も褒めます!!
③プレッシャーを与えすぎない
つい「ちゃんとしなさい」「早くやって!」と言ってしまうこと、ありますよね。
でも、子どもはその一言で大きなプレッシャーを感じてしまうこともあります。
特に、真面目で頑張り屋の子ほど、「ちゃんとやらなきゃ」と自分を追い込みがちなんです。
「失敗しても大丈夫」「できなくても、あなたは大切な存在だよ」というメッセージを、
日ごろから伝えるようにしてあげてください。
完璧じゃなくてもいい、がんばる気持ちを大切にすることで、心がずっと楽になりますよ。
「ちゃんとしなさい」「早くやって!」と伝えたい気持ちはわかりますが、子どもにプレッシャーを与えずに行動を促すには、少し工夫が必要です。
伝え方のポイント
- 具体的に伝える
「ちゃんとしなさい」ではなく、「〇〇をこうするといいよ」と具体的な指示を出すことで、子どもは何をすればいいのか明確に理解できます。 - タイミングを工夫する
動き始める前に「あと〇分で始めるよ」と伝えたり、時計を使って視覚的に時間の感覚をつかませると、急かされるストレスを減らせます。 - 共感してから促す
「今遊びたいよね。でも、これを終わらせたらもっと楽しめるよ!」と気持ちを受け止めた上で行動の重要性を伝えると、抵抗感が減ります。 - 成功体験を積ませる
「今すぐやったからスムーズに終わったね!」など、小さな成功を言葉にすることで、次回もスムーズに行動しやすくなります。
④失敗を受け止める環境づくり
失敗したときに「なんでこんなことしたの!?」と怒られると、子どもはもう挑戦しようとしなくなっちゃうんです。
だから、失敗を「成長のチャンス」として受け止められる環境づくりがすごく大事なんですよ。
たとえば、工作がうまくできなかったとき、「失敗しちゃったね。でもやってみたのはすごいよ!」と声をかけるだけで、気持ちの落ち込みがグンと変わります。
親自身が「ミスしても大丈夫」という空気を出しておくと、子どもも自然とチャレンジできるようになります。
心の体調管理って、こういう日常の積み重ねがすごく効くんですよ~。
失敗を「成長のチャンス」として受け止められる環境づくり、大切ですね。
1. まずは気持ちを受け止める
「うまくいかなかったね」「悔しい気持ちもあるよね」と共感することで、子どもは安心して感情を表現できます。焦って「次どうする?」より、まず気持ちを認めることが大切です。
2. どんな挑戦だったのかを認める
「こうやって試してみたのはすごいよ」「工夫したところがいいね」と、行動や考え方を具体的に褒めると、自分の挑戦に意味を感じられます。
3. 失敗の先にある「学び」を一緒に考える
「どこが難しかったかな?」「次はどうやってみる?」と話し合いながら、失敗を改善のチャンスにする習慣をつけると、前向きにチャレンジし続けられます。
4. 親自身も「ミスしても大丈夫」を実践する
親が「うっかりミスしちゃった!次はこうしてみよう」と自然に言葉にすると、子どもも「失敗は学びの一部」と感じやすくなります。
⑤無理せず休ませる選択肢を持つ
「学校は絶対休んじゃダメ!」って思ってませんか?
もちろん、基本は登校が大事だけど、心や体がしんどいときは「休む」選択肢があるという安心感も必要なんです。
登校しぶりや元気のなさが続くときは、「今日はおうちでゆっくりしようか」と一息つかせてあげるのも立派なケアです。
「休んだら怒られる」と思っていると、どんどん心が追い込まれてしまいます。
子どものSOSを見逃さないように、柔軟に対応してあげてくださいね。
専門職の視点から見ると、子どもの「登校しぶり」や「元気のなさ」は、単なる怠けではなく、
心理的・身体的な負担のサインである可能性があります。
子どもの精神的健康を守るためには、柔軟な対応と適切なサポートが重要です。
1. 登校ストレスと精神的な影響
学校生活は、学習だけでなく対人関係のストレスや期待に応えるプレッシャーを伴います。精神保健福祉士の観点では、登校しぶりは 適応障害や不安障害の初期サイン であることも多く、無理に登校を強要すると心的負担が増し、より深刻な問題に発展することがあります。
2. 休息の心理的意義
「休む=甘え」ではなく、 心理的安全を確保する手段 です。心が疲弊した状態で学校に通い続けると、慢性的なストレスが蓄積し、自尊感情の低下や自己効力感の喪失につながることがあります。「休んでも大丈夫」という選択肢があることで、子どもは安心し、自分の気持ちを整える時間を持てます。
3. 親の関わりと環境づくり
精神保健福祉士の立場からは、親が 子どもの気持ちを受け止め、対話を通じて安心感を与える ことが重要だと考えます。例えば、
- 「今日はどうしたい?」と、子どもの気持ちを確認する
- 「あなたの気持ちを大事にしたいよ」と 無条件の受容 を伝える
- 「いつも頑張ってるね」と、登校している努力を認める
4. 登校支援の柔軟な選択肢
無理に「学校に行かせること」だけが解決ではなく、
- 保健室登校や相談室を活用する
- 教師やスクールカウンセラーとの連携を図る
- フリースクールなどの代替教育機関を検討する
このような対応も視野に入れながら、子どもの状況に合わせたサポートをすることが重要です。「休んだからダメ」という固定観念ではなく、 子どもの心の回復を優先する姿勢 を持つことが、長期的に健全な成長につながります。
体調不良時の正しい対応方法3ステップ
体調不良時の正しい対応方法3ステップについて解説します。
小学生の子どもが「なんか調子悪そう…」となったとき、どう対応すればいいか悩みますよね。
慌てず、でも的確に行動するために、基本の3ステップを押さえておきましょう。
①症状に応じた初期対応をする
まずは、どんな症状が出ているかを冷静に観察しましょう。
熱、咳、腹痛、吐き気、下痢…それぞれ対応が異なるので、症状の種類と強さを見極めることが大切です。
たとえば微熱(37.5℃程度)でも元気がない場合は、すぐに安静にさせて体を休ませてあげましょう。
寒気があるなら布団で温かく、吐き気があるなら無理に食べさせず、こまめに水分補給を意識することがポイントです。
特に急にぐったりしたり、ぼーっとした様子があるときは要注意。
早めに様子を見る体制を取ってくださいね。
②登校判断の目安を把握しておく
朝、体温が微妙だったり、ちょっとだるそうにしているとき、「これ、学校行かせていいのかな?」って迷いますよね。
基本的な目安としては、以下のようなガイドがあります:
| 症状 | 登校の目安 |
|---|---|
| 発熱(37.5℃以上) | 基本的にお休み |
| 咳・鼻水だけ | 元気なら登校可、様子見 |
| 吐き気・下痢 | 症状が治まるまではお休み |
| インフル・感染症疑い | 医師の指示に従う(出席停止) |
学校ごとに判断基準がある場合もあるので、年間のおたよりや保健だよりをチェックしておくと安心です。
無理に行かせて悪化するより、「休んでもいいよ」と言える余裕が大事です。
もちろん共働きワーママさんは難しいですよね。
病児保育なども検討してくださいね。
③病院を受診するタイミングを知る
「受診するほどでもないかな?」「様子を見ても大丈夫かな?」と迷うこと、ありますよね。
でも、小さな体の変化が重症化につながることもあるため、適切なタイミングでの受診がとても大切です。
実際に、厚生労働省が案内している「子どもの救急」では、
次のような症状があった場合には、すぐに医療機関を受診することが推奨されています。
- 呼吸が速い、または苦しそうにしている
- ぐったりしていて、顔色が悪い
- 水分が摂れない、もしくは吐いてしまう
- けいれんが5分以上続いている
また、日本小児科学会が監修する「こどもの救急」サイトでは、症状別に対応の緊急度が示されており、「すぐに病院へ」「翌日でOK」「様子見でよい」などの判断をサポートしてくれます。
たとえば、38度以上の発熱が1日以上続く、食欲が明らかにない、明らかな脱水症状がある(口が渇く・おしっこが出ない)などの場合も、受診の目安とされています。
「これくらいなら大丈夫かな」と思っても、迷ったら#8000(こども医療電話相談)を活用するのもおすすめです。
「相談するだけ」でも気持ちがぐっと軽くなりますし、早めの対応が子どもの回復にもつながりますよ。
📄参考リンク:
子どもの心と体を守るために親ができること5選
子どもの心と体を守るために親ができること5選について解説します。
子どもの体調管理って、どうしても「子どもだけを何とかしなきゃ!」と思いがちなんですが、
実は親の関わり方や家庭の空気がすごく影響します。
だからこそ、日常の中で親ができるちょっとした行動を見直すことが、子どもの健康につながっていきますよ。
①家族で健康意識を共有する
健康管理って、家族みんなの「共通意識」があると、ぐっとスムーズになります。
たとえば、「夜は早く寝るようにしよう」「手洗いは玄関で必ず」「朝はみんなでラジオ体操」なんて決まりごとを、親だけじゃなく子ども自身も理解して守れるようにする。
家族で一緒に決めたルールなら、子どもも素直に受け入れやすいですし、「なんで自分だけ?」という反発も起きにくくなります。
とくに兄弟がいる場合、上の子がやっていると下の子も自然と真似してくれるので、全体で意識を育てていくのが理想です。
“健康は家族全員のテーマ”っていう感覚を持てると、自然に体調管理も習慣化されますね!
②子ども自身のセルフケア力を育てる
小学生とはいえ、「自分の体調を自分で見る力」って、意外と育てられます。
たとえば「今日はちょっと頭が痛いかも」「いつもより疲れてるかも」など、自分の状態を感じ取って、親に伝える力を育ててあげることが大切です。
そのためには、「どうしたの?」「どんな感じ?」と、体調について聞く時間を日常に取り入れることがポイント。
さらに、「体調が悪いときはどうする?」と一緒に考えておくことで、いざというときに落ち着いて行動できるようになります。
こうした習慣は、中学生・高校生になってからもずっと役立つ一生ものの力になりますよ!
③ストレス発散の方法を一緒に見つける
実は、ストレスって子どもにとっても結構大きなテーマなんです。
特に学校生活って、小学生なりに人間関係や勉強で悩みやすいんですよね。
だから、家では「何かあったら話していいよ」という空気を作るとともに、
子どもが気分転換できる“ストレス発散方法”を一緒に見つけておくと安心です。
たとえば、お絵描き、ダンス、外遊び、ゲーム、ぬいぐるみとのおしゃべり…なんでもOK!
「これをやるとスッキリする」というものを持っている子は、
ちょっと落ち込んでも自分で立て直す力がついてきます。
ポイントは1つ2つではなくて複数のストレス発散方法を見つけておくこと。
ストレスコーピング(ストレス対処方法)については後日また記事を書きますが、
今は以下4つだけ覚えておいてください!
- 動的コーピング(体を動かしてストレス解消)
→ ジョギングやダンスをして気分をリフレッシュする。特にリズムのある運動は、心を前向きにする効果が期待できます。 - 静的コーピング(落ち着いてストレスを受け止める)
→ 瞑想や深呼吸をして気持ちを整える。ゆっくりした呼吸を意識することで、不安を和らげることができます。 - 浄化系コーピング(気持ちを整理し、デトックスする)
→ 日記を書いて、頭の中のモヤモヤを言葉にする。感情を言語化することで、自分の気持ちを客観的に見つめることができます。 - 発散系コーピング(強い感情を外に出してストレスを手放す)
→ カラオケで大声を出して歌う。声を出すことで、心の中に溜まったものを外へ解放できます。
④医療機関やスクールカウンセラーと連携する
親だけで頑張りすぎないことも、すごく大切です。
特に心や体に不安が続く場合は、かかりつけの小児科や、学校の保健室、スクールカウンセラーなどと連携していくのが安心です。
「こんなことで相談していいのかな?」と思う内容でも、専門家はしっかり対応してくれるので遠慮せず頼ってください。
定期的に通える相談先があるだけでも、親としての不安が和らぎますし、子どもも「自分のことを大人が一緒に考えてくれるんだ」と感じて心が安定します。
孤立せず、みんなで支える体制をつくることが一番の安心につながりますよ。
⑤親も自分自身の健康管理を忘れない
最後に大事なこと、それは「親自身の体調も大切にすること」です!
忙しさで自分のことを後回しにしがちですが、親が疲れていると、どうしてもイライラしたり、子どもの変化に気づきにくくなったりしちゃうんですよね。
「ちょっと疲れてるな」と感じたら、無理せず休む。
しっかり睡眠をとる。好きなことをしてリフレッシュする。
こうしたセルフケアをすることが、結果的に子どもにとっても安心できる家庭環境につながります。
「親だって人間なんだよ」という姿を見せることで、
子どもにも「休むこと=悪いことじゃない」と伝わりますよ。
まとめ|小学生の子どもの心と体の体調管理を整えるために大切なこと
| 体調管理の基本5つ |
|---|
| ①手洗い・うがいを習慣化する |
| ②規則正しい生活リズムを作る |
| ③栄養バランスの取れた食事を意識する |
| ④適度な運動で免疫力アップ |
| ⑤十分な睡眠時間を確保する |
小学生の体と心の体調管理は、日々の小さな習慣の積み重ねから始まります。
特別なことをしなくても、手洗いやうがい、食事や睡眠などの基本を見直すだけで、ぐっと健康の土台が整ってきます。
また、心のケアにも目を向けることで、より安心して毎日を過ごせるようになります。
体調不良の際も、焦らず落ち着いて対応できるよう、日頃から親子で準備しておきましょう。
「うちの子、大丈夫かな?」と不安になったときに、この記事が少しでも安心材料になれば嬉しいです。
▼子どもの健康と心の発達に関する公式情報はこちらも参考にどうぞ:
- 厚生労働省:子どもの健康支援
- 子どものメンタルヘルス|こころもメンテしよう 厚生労働省
- 健康づくりのための睡眠ガイド2023 厚生労働省
- 子どもの体力向上ホームページ
- 令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
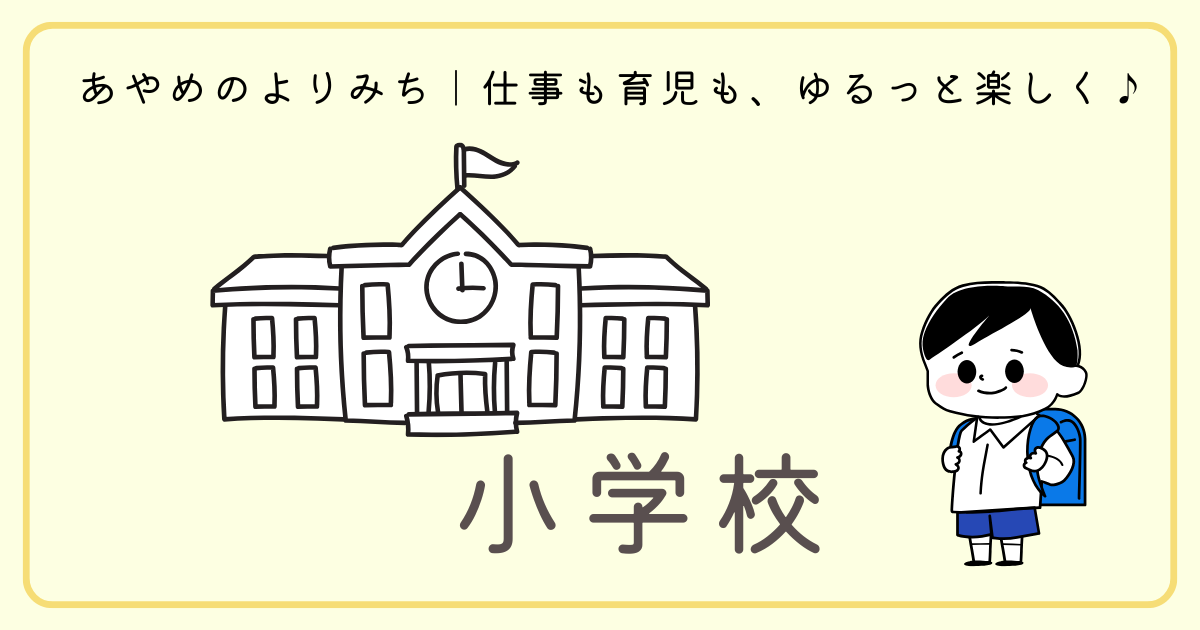



コメント