「子どもに約束を守ってもらう方法が知りたい」と悩んでいませんか?
毎日頑張って伝えているのに、なかなか思うように約束を守ってくれないと、
ついイライラしてしまうこともありますよね。
実は、子どもが自然と約束を守れるようになるためには、
ちょっとした工夫と、親の関わり方がとても大きな鍵を握っています。
この記事では、心理学的な知見ももとに、子どもが自分から約束を守りたくなる関わり方や、
年齢に応じた伝え方、習慣化のコツまで、丁寧に解説していきます。
今日からできる具体的なステップをたくさんご紹介していますので、
ぜひ最後まで読んで、親子の毎日をもっと楽しく、笑顔にしていきましょう。
子どもに約束を守ってもらう方法7選
子どもに約束を守ってもらうために、親ができる対応を丁寧にお伝えします。
それでは、一つずつ丁寧に見ていきましょう。
①約束の意味をわかりやすく伝える
まず、子どもにとって「約束」という言葉は、思っている以上に抽象的なものです。
ですから、伝えるときは「お互いにやると決めたことを守ること」と、
できるだけシンプルな言葉を選びましょう。
たとえば、
「夕ごはんのあとに片付けをするって、ふたりで決めたよね。だから、約束守ろうね」と、
具体的な場面に結びつけると理解しやすくなります。
子どもが自分の行動と約束を自然に結びつけられるようになると、
守ろうという気持ちも育っていきます。
小さなことでも、きちんと意味を伝える姿勢が大切です。
②子どもの年齢に合わせて内容を調整する
子どもにとって無理のない約束をすることが大切です。
まだ年齢が小さいうち(未就学児)は、
長期的なことや複雑なことはイメージしづらいので、短く、すぐにできる約束から始めましょう。
「今日のお片付けを一緒にやろうね」という一日単位の約束が良い例です。
小学生以上になれば、少しずつ理由を添えて説明することで、約束の意義を理解できるようになります。
年齢や発達に合わせた伝え方を意識すると、子どもも無理なく達成できるようになります。
③守れる小さな約束から始める
最初から大きな約束を求めると、子どもはうまくいかずに自信をなくしてしまいます。
ですから、まずは必ず達成できる小さな約束を設定しましょう。
たとえば、「使ったおもちゃは一つだけでもいいから片付けようね」という程度でも構いません。
「できた」という成功体験を積み重ねることが、やがて「約束は守るものだ」という意識につながっていきます。
④約束を紙に書いて「見える化」する
言葉だけの約束は、時間がたつと忘れてしまうことがよくあります。
そんなときは、約束を紙に書いて、目に見える場所に貼ると効果的です。
「ごはんを食べたら手を洗う」など、
短い文とイラストを添えてリビングに貼るだけでも、自然に意識を向けることができます。
子ども自身が絵を描いたり、シールを貼ったりすると、
さらに自分ごととして捉えられるようになります。
目に見えるかたちにすることで、約束がぐっと身近なものになります。
⑤守れたときはしっかり褒める
子どもが約束を守れたときは、できるだけ早く(すぐに)
具体的に褒めてあげてください。
たとえば、「おもちゃをきれいに片付けたね。ママ、とても嬉しいよ」と、
行動と気持ちをセットで伝えます。
子どもは大人の反応を通して、「この行動は良いことなんだ」と理解していきます。
褒められることで自信が育ち、さらに次も守ろうという意欲につながります。
小さなことでも、見逃さずに声をかけることが大切です。
⑥守れなかったときは冷静に対応する
もし約束を守れなかったとしても、感情的に叱る必要はありません。
「どうしてできなかったのかな?」と、まずは子どもの気持ちを聞いてあげましょう。
責めるのではなく、
一緒に原因を考えることで、次はどうすればいいかを子ども自身が見つけやすくなります。
できなかったことに焦点を当てるのではなく、次に向けて前向きな気持ちを育てていくことが大切です。
冷静な対応が、信頼関係を壊さず、成長につなげる大事なステップになります。
⑦親自身が約束を守る姿勢を見せる
子どもに約束を守ってほしいなら、
まず親自身が約束を守る姿を見せることが基本です。
たとえば、「あとで一緒に遊ぼうね」と言ったなら、たとえ忙しくてもきちんと時間を作りましょう。
子どもは親の行動をよく見ています。
大人が約束を大切にしている姿を見せることで、「約束は守るものだ」という意識が自然に育っていきます。
言葉よりも、行動で教えることが、何よりも子どもの心に届きます。
親の対応次第で子どもは変わる
親の対応一つで、子どもは驚くほど大きく変わります。
それでは、順番に詳しくご紹介していきます。
①親の言動が手本になる
子どもに「約束を守ること」を身につけてもらうために、
一番効果的なのは、親自身が日常の中で約束を守る姿を見せることです。
言葉で「約束は大事だよ」と教えるよりも、行動で示す方が、子どもの心には深く届きます。
たとえば、「あとで絵本を読もうね」と言ったら、どんなに忙しくても必ず時間を作って読んであげること。
「今日は18時にご飯だよ」と約束したなら、できる限りその時間を守ろうとする姿勢を見せること。
子どもは、そういった大人の一貫した行動を、無意識のうちにしっかり吸収しています。
ここで特に気をつけたいのは、「大人の都合で約束の解釈を変えない」ということです。
たとえば、忙しくなったからといって
「やっぱり今日はなしね」と簡単に約束を変えてしまうと、
子どもは「約束は守らなくてもいいんだ」と学んでしまいます。
どうしても守れない事情ができたときは、
「本当は約束を守りたかったけれど、今日は難しくなってしまった」と、きちんと理由を説明しましょう。
そして、次にどうするかを一緒に決め直すことも大切です。
大人の側が約束を軽く扱わず、
誠実に向き合う姿を見せることが、子どもにとって最高のお手本になります。
また、親自身もミスをすることはあります。
そんなときに、「ごめんね、今日は約束を守れなかったね」と素直に謝ることも、子どもにとって大切な学びになります。
完璧である必要はありません。
約束を守ろうと努力する姿勢と、誠実に向き合う態度こそが、子どもに約束の本当の意味を伝えていくのです。
②感情よりも冷静な対応を意識する
子どもが約束を破ったり、思うように動いてくれないと、つい感情的になりたくなることもあります。
ですが、大人が感情を爆発させると、子どもはその場をやり過ごすことばかりを考えてしまいます。
大切なのは、落ち着いた態度で「どうしたのかな?」と問いかけることです。
子ども自身が、自分の行動を振り返る時間を持てるように、冷静に関わっていきましょう。
親の冷静さは、子どもに安心感を与え、前向きな行動を引き出す力になります。
③一貫性のあるルールが大切
ルールは、言ったり言わなかったりするものではなく、常に一貫して伝えることが大切です。
「今日はいいけど明日はダメ」といった対応をしてしまうと、子どもは混乱してしまいます。
たとえば「ゲームは宿題が終わってから」と決めたら、どんな日でもそのルールを守るようにしましょう。
ルールが一貫していると、子どもも次にどうすればいいかがわかりやすくなり、自分で判断できる力も育ちます。
小さなことでも、ルールをぶらさない意識を持つことが大切です。
④「ダメ」より「どうすればいいか」を伝える
子どもに注意するとき、つい「ダメ!」と否定から入ってしまうことがあります。
しかし、否定だけでは、子どもはどう行動すればよいかを学びにくくなってしまいます。
たとえば、「おもちゃを散らかしてダメ!」ではなく、「遊び終わったらこの箱に入れようね」と伝えるだけで、子どもは次に取るべき行動を理解しやすくなります。
できるだけポジティブな指示に変えることを意識しましょう。
子どもは、「何をしてほしいか」を具体的に教えてもらうことで、自分から行動しやすくなります。
年齢別!子どもへの約束の伝え方
子どもの年齢や発達段階に合わせて、伝え方を工夫することが大切です。
それぞれの年齢に応じたコツを詳しくお伝えします。
①未就学児には具体的で短い約束を
未就学児の場合、抽象的な約束はまだ理解が難しいことが多いです。
ですから、「片付けをちゃんとしようね」ではなく、「遊んだブロックをこの箱に入れようね」というように、具体的な行動を示してあげましょう。
また、一度にたくさんのルールを伝えず、ひとつの約束に絞ることが大切です。
短く、シンプルな言葉で、行動をイメージできるように伝えると、子どもも安心して動くことができます。
達成できたときには、すぐにたくさん褒めて、自信を積み重ねていきましょう。
②小学生には納得できる理由もセットで
小学生になると、理由や背景を理解する力が少しずつ育ってきます。
この時期の子どもには、単に「こうしなさい」と命令するだけでなく、
「なぜその約束が大切なのか」も一緒に伝えてあげましょう。
たとえば、「宿題をしてから遊ぶのは、頭が元気なうちに勉強した方が早く終わるからだよ」と、理由を説明すると納得しやすくなります。
納得できると、子ども自身が「やろう」と思えるので、約束を守る意識も高まります。
上手に説明することで、子どもの自主性も育てることができます。
③中学生には対等な関係を意識する
中学生くらいになると、指示されることに反発したくなる時期に入ります。
この年代には、親が一方的に約束を押し付けるのではなく、対話の中で一緒にルールを決める姿勢が大切です。
たとえば、「スマホは何時までに使い終わるか、一緒に決めようか」というように、
子どもにも意見を求めながら話し合ってルールを作ることが効果的です。
自分で決めたルールには、責任感を持って取り組むようになります。
大人と対等に話し合う経験が、子どもの自己決定力や自立心を育てていきます。
親も意識したい心構え5つ
子どもに約束を守らせるためには、親自身の心の持ち方もとても大切です。
それでは、一つひとつ、心に留めておきたいポイントを紹介します。
①完璧を求めすぎない
子どもに何かを教えるとき、つい「完璧にやってほしい」と思ってしまうことがあります。
ですが、子どもは大人と違い、まだ発達の途中にいます。
毎回うまくいくわけではないことを、親自身が受け止めることが大切です。
多少の失敗や抜け漏れがあっても、「成長の一環」と考えることで、親も子どもも気持ちが楽になります。
完璧を求めるより、努力している過程を認めることを意識していきましょう。
②失敗も成長の一部と考える
約束を破ってしまったり、できなかったりすることも、子どもにとっては大切な学びの一つです。
失敗を責めるのではなく、「なぜうまくいかなかったのか」を一緒に考える機会に変えていきましょう。
「失敗しても、やり直せる」「また次がある」と伝えることで、子どもは挑戦を恐れずに前向きに取り組むようになります。
成長には、必ず試行錯誤のプロセスが必要です。
失敗を温かく受け止めることで、子どものたくましさが育っていきます。
③「叱る」より「対話する」を意識する
約束を守れなかったとき、感情に任せて叱ってしまうと、子どもは「怒られるから」と形だけ行動するようになってしまいます。
大切なのは、叱るよりも、子どもの気持ちに寄り添って対話することです。
「どうして守れなかったのかな?」「次はどうすればできるかな?」と、問いかけながら一緒に考えていくと、子ども自身が問題を自分ごととして捉えられるようになります。
対話の積み重ねは、信頼関係を強くし、子どもの自己解決力も育てます。
穏やかに話し合う時間を大切にしましょう。
④子どもを信じる気持ちを持つ
子どもに対して「どうせできないだろう」と疑う気持ちがあると、それは言葉や態度に表れてしまいます。
逆に、親が「あなたならできる」と信じて接すると、子どもはその信頼に応えようと努力します。
たとえ途中でつまずいても、「きっとできるよ」と温かく励まし続けることが、子どもの心の支えになります。
信じるという姿勢は、子どもにとって何よりの力になります。
子どもの可能性を、親自身が一番に信じてあげましょう。
⑤時間をかけて育てる姿勢が大切
約束を守る力は、一朝一夕で身につくものではありません。
失敗しながら、少しずつ覚えていくものです。
焦らず、長い目で見守る姿勢を持つことがとても大切です。
たとえ今日うまくいかなかったとしても、続けていくうちに、必ず子どもは成長していきます。
時間をかけて、一緒に歩んでいく気持ちを大切にしましょう。
約束を習慣化させるための工夫
一度きりではなく、子どもが自然と約束を守れるようになるには、習慣化の工夫が欠かせません。
楽しく取り組める工夫を一緒に考えていきましょう。
①チェックシートやカレンダーを使う
子どもにとって、目に見える成果は大きなモチベーションになります。
たとえば、約束を守れた日はカレンダーにシールを貼る、専用のチェックシートに〇をつけるなど、視覚的に達成感を味わえる仕組みを作りましょう。
達成の積み重ねが見えることで、子ども自身も「続けたい」という気持ちが自然に育っていきます。
この方法は、行動療法でも推奨されている習慣形成のテクニックの一つです。
できるだけシンプルで楽しいデザインを取り入れると、子どもも前向きに取り組みやすくなります。
②ゲーム感覚で続けられる工夫をする
ただ「守りなさい」と言われるだけでは、子どもはなかなか継続できません。
そこで、約束を守ることをゲーム感覚に変えてみましょう。
たとえば、「おもちゃを片付けるタイムアタック」をして、片付け時間を測ったり、できたら特別なスタンプを集めるなど、遊び心を加える工夫が効果的です。
楽しいという感情は、行動の定着を促進します。
子どもが「やらされている」ではなく、「自分からやりたい」と思える仕掛けを作ることがポイントです。
③成功体験を積ませて自信につなげる
約束を守る経験を積み重ねることは、子どもの自己肯定感を育てるうえでも非常に重要です。
小さな成功でも「できたね」「がんばったね」と認めることで、子どもは自信を持ち、次もがんばろうという意欲が高まります。
初めから完璧を目指す必要はありません。
「昨日より5分早く片付けができた」など、ほんの少しの進歩でもしっかり言葉にして伝えてあげましょう。
子どもにとって、
「自分はできる」という感覚を育むことが、何よりも大切な財産になります。
④ご褒美制度はルール化して活用
ご褒美を取り入れることも、習慣化を助ける有効な方法です。
ただし、気まぐれに与えるのではなく、あらかじめルールを決めておくことが大切です。
たとえば、「1週間毎日お片付けできたら好きな絵本を1冊買おうね」といった具体的なルールを作ると、子どもは目標に向かって主体的に努力するようになります。
ご褒美は、子どもが「できた」ことを振り返るきっかけにもなります。
小さな成功を積み重ね、ご褒美を上手に活用しながら、楽しく約束を守る力を育てていきましょう。
まとめ|子どもに約束を守ってもらう方法
| ポイント | 詳しく読む |
|---|---|
| 約束の意味をわかりやすく伝える | こちら |
| 子どもの年齢に合わせて内容を調整する | こちら |
| 守れる小さな約束から始める | こちら |
| 約束を紙に書いて「見える化」する | こちら |
| 守れたときはしっかり褒める | こちら |
| 守れなかったときは冷静に対応する | こちら |
| 親自身が約束を守る姿勢を見せる | こちら |
子どもに約束を守ってもらうためには、日々の積み重ねと、親自身の関わり方がとても大切です。
完璧を求めず、できたことを一つずつ認めていく姿勢が、子どもの自信と意欲を育てていきます。
親も子どもも成長していく過程を、温かく見守りながら、一緒に歩んでいけたら素敵ですね。
この記事が、少しでもあなたとお子さんの毎日に役立てばうれしいです。


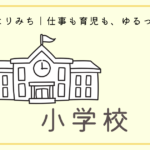
コメント