ファミサポって実際どうなの?
「役所でたまに見かけるファミサポって、一体どんなサービス?」
子育て中の皆さんなら、一度は目にしたことがあるかもしれません。ファミリーサポートセンター事業、通称「ファミサポ」。地域の子育てを助け合う、心強い存在です。
しかし、
- 「具体的にどんな時に使えるの?」
- 「利用料金はどれくらい?」
- 「実際、利用者の評判はどうなの?」
など、疑問も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、社会福祉士の国家資格を持ち、実際に社会福祉協議会での実習経験もある私が、
ファミサポの内部事情から活用法まで徹底解説します!
ファミサポとは?子育て共助の仕組みを詳しく解説
ファミサポ(ファミリー・サポート・センター)は、地域の中で子育ての援助を受けたい人(依頼会員)と、行いたい人(提供会員)が会員となり、助け合う会員制の仕組みです。
ファミサポで対応可能な主なサービス内容
例えば、
- 保育園や幼稚園、習い事などの送迎
- 保護者の残業や急用時の子どもの預かり
- 冠婚葬祭やリフレッシュしたい時の一時的な預かり
- 兄弟の学校行事に参加する際の下の子の預かり
- 買い物や美容院などの外出時のサポート
など、様々な場面で利用できます。地域の「おかあさん」的存在が、あなたの子育てを柔軟にサポートしてくれるのです。
ファミサポでできないこと(利用制限の知識)
- 病院の受診(医療行為に関わるため)
- 体調不良時の預かり(病児・病後児保育の専門サービスを利用)
- 宿泊を伴うもの(原則として日帰りのみ)
- 依頼会員不在の自宅での預かり(※ただし外出先へ連れ出すなどは可能)
- 重度の障害がある子どもの専門的ケア(専門機関の利用や別のサービスを利用)
ファミサポの正しい使い方と登録から利用までの流れ
ファミサポ利用の6ステップ
- 会員登録:お住まいの地域のファミリーサポートセンターに連絡し、会員登録を行います。多くの場合、説明会への参加が必要です。
- 援助依頼:援助が必要な日時や内容をセンターに伝えます。できるだけ具体的に希望を伝えましょう。
- マッチング:センターが条件に合う提供会員を探し、マッチングします。地域や時間帯によっては時間がかかる場合も。
- 事前打ち合わせ:依頼会員と提供会員が事前に顔合わせと打ち合わせを行います。子どもの特性やアレルギー情報なども共有しましょう。
- 援助開始:打ち合わせ内容に基づき、援助が開始されます。初めての場合は短時間から始めるのがおすすめです。
- 利用料金の支払い:利用後、所定の料金を提供会員に直接支払います。領収書をもらうことも忘れずに。
ファミサポの料金体系を徹底解説
料金は地域や援助内容によって異なりますが、1時間あたり500円~1,000円程度が目安です。詳細はお住まいの地域のセンターにお問い合わせください。
私が今まで住んでいた市では、平日の日中が1時間あたり500円、早朝・夜間・休日は1時間あたり800円でした。
このほか、以下の点に注意が必要です:
- 援助内容によって金額が変わる(送迎のみ、預かりのみ、両方など)
- 実費の交通費代が追加される場合がある
- きょうだい同時預かりの場合は追加料金が発生する場合がある(2人目半額など)
- キャンセル料が発生する場合がある(地域による)
ファミサポ利用のメリットとデメリット~実体験から語る真実~
ファミサポの3つの大きなメリット
- 地域の人がサポートしてくれる安心感:顔見知りの地域の方がサポートしてくれるため、母親的な存在として精神的に助けられる場面も多いです。子育ての知恵や地域の情報も教えてもらえることも。
- 柔軟な対応が可能:急な残業や突発的な用事にも、可能な範囲で対応してくれます。保育園の延長保育よりも柔軟な場合が多いです。
- 比較的安価に利用できる:民間のベビーシッターと比較すると、かなりリーズナブルな料金設定です。公的サービスならではの安心感もあります。
ファミサポ利用時の注意点と対策
- 提供会員の質にばらつきがある場合がある:研修を受けているとはいえ、保育の専門家とは限りません。事前にしっかり打ち合わせをしましょう。
- マッチングに時間がかかる場合がある:特に初回は時間に余裕を持って依頼しましょう。緊急時の対応は難しい場合があります。
- 人気のある提供会員は予約が取りにくい:定期的に利用したい場合は、早めに予約を入れることをおすすめします。
- 提供会員が見つからない場合がある:地域や時間帯によっては、対応可能な提供会員がいない場合も。複数の預け先を確保しておくことが大切です。
社会福祉士が教えるファミサポの内部事情
社会福祉協議会での実習経験から、ファミサポの内部事情も少しだけお話します。
- 提供会員の多様性:子育て経験があり子育てが落ち着いてきた主婦の方や、保育士・看護師などの資格を持つ方、定年退職後の方など、様々なバックグラウンドの方がいます。
- 提供会員の研修制度:資格がない方でも提供会員の研修やフォローアップ講習を定期的に実施しています。研修を受けた会員だけが提供会員になれるので、全くの素人が行うことはありません。
- 提供会員の減少と高齢化:提供会員も年々減少傾向にあり、かつ高齢化が進んでいます。
- 地域差の実態:地域によっては、提供会員が不足している場合もあります。特に都市部以外では、マッチングが難しいケースも。
- 共助(ともにたすけあう)の理念:ファミサポは単なるサービスではなく、地域で子育てを支え合う「共助」の視点で運営されています。お互いさまの気持ちが大切です。
ファミサポ活用体験記~4つの実例から学ぶ効果的な使い方~
実は、私もファミサポを利用した経験があります。実際に体験したからこそわかる、リアルな活用法をお伝えします。
通院サポートで医療ケアを継続
定期的な通院が必要な時、子どもを預かってもらいました。病院には連れていくことができず、家族も休めないときはかなり重宝しました。
リフレッシュタイムの確保で育児ストレス軽減
たまには一人の時間が欲しくなるもの。そんな時、数時間でも子どもを預かってもらえると、心身ともにリフレッシュできます。何も考えず寝ました。
産後の上の子ケアで家族の安定を実現
私は下の子の産後に、上の子と一緒に遊んでもらいました。上の子は特別な時間を過ごせて嬉しそうでしたし、私は赤ちゃんのケアに集中できました。家族全体のバランスを保つのに役立ちました。
産前産後ヘルパーは、妊娠中の特別な事情、もしくは産後5カ月以内のママと赤ちゃんに対して家事や育児の軽減を目的としヘルパーを派遣する事業です。
こっちでも上の子と遊んでくれることはありますが回数制限がありやや使いにくい。
また、こっちは家事(ご飯作ったりおふろをわかしたり)育児(おむつを替えたり、ミルクの準備をしたり)をしてくれますが、ファミサポは家事育児ができません。
行事参加で子どもの成長を見守る
上の子の行事に参加する際、下の子を預かってもらい、行事に集中することができました。子どもにとっても、親が自分だけに集中してくれる時間は特別なものです。思い出に残る行事を見逃さずに済みましたし、下の子大丈夫かな?と心配することなく行事に参加できました。
ファミサポをもっと効果的に活用するための5つのコツ
1. 登録はできるだけ早めに済ませておく
使う予定がなくても登録だけはしておくことをおすすめします。
いざというときに登録していないと、すぐに利用できません。
登録には説明会参加などの手続きが必要で、時間がかかる場合があります。
2. 計画的な予約で確実にサポートを確保
提供会員にも予定があるので、できるだけ早めに予約を入れましょう。
特に長期休暇期間は競争率が高くなります。
定期的な利用なら、月単位でまとめて予約するのも一つの方法です。
3. 事前打ち合わせでミスマッチを防止
事前打ち合わせでは、希望や不安をしっかり伝えることが大切です。
子どもの好きなものや苦手なもの、アレルギー情報、緊急連絡先など、必要な情報を漏れなく共有しましょう。
できることとできないことをはっきりさせておくことで、トラブルを防げます。
4. 複数の提供会員と関係を築いておく
可能であれば、複数の提供会員と顔合わせをしておくと安心です。
主に頼む方が都合がつかない場合のバックアップとして、別の提供会員にもお願いできるようにしておきましょう。
5. 感謝の気持ちを忘れずに
料金を支払うサービスとはいえ、感謝の気持ちを伝えることは大切です。
子どもの様子を報告したり、簡単なお礼の言葉を伝えたりすることで、良好な関係が続きます。
継続的に利用する場合は特に重要です。
まとめ:ファミサポを味方につけて、もっと楽しい子育てを
ファミサポは、子育ての強い味方です。適切に活用すれば、親のストレス軽減だけでなく、子どもにとっても地域の大人との関わりという貴重な経験になります。
「完璧な親」を目指すのではなく、地域の力も借りながら、無理なく楽しく子育てをしていきましょう。ファミサポという選択肢を知っているだけで、子育ての視野が広がるはずです。
まずは、お住まいの地域のファミリーサポートセンターに問い合わせてみてください。新しい子育ての可能性が広がるかもしれません。
詳しい情報はこちら
- 一般財団法人 女性労働協会:ファミリーサポートセンター事業 – 一般財団法人 女性労働協会
- お住まいの自治体のホームページ:「〇〇市 ファミリーサポートセンター」「〇〇市 ファミサポ」で検索

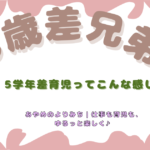
コメント