放課後、「お母さん、お子さんの最近の様子どうですか?」と学校から電話がかかってきた。
この時点で、親としては“何かあったな”と直感しますよね。
案の定、先生からは「お子さんが友達をケガさせたようです」と伝えられ、
動揺と混乱が一気に押し寄せました。
子どもが“加害者”になるなんて、考えたこともなかった――そう感じたのが正直な気持ちです。
けれど、事態は待ってはくれません。
まずは状況を整理し、学校と連携しながら、相手方への誠意ある対応を考えなければなりませんでした。
この記事では、実際に私が体験した流れをもとに、
初動の対応から謝罪、必要だった備えまでをまとめました。
「もしも同じことが起きたら…」そんな不安を抱える親御さんの参考になれば幸いです。
子どもが友達をケガさせた…親として最初にすべきこと
①事実確認:子どもと先生から冷静に情報を集める
ある日、突然学校の先生から連絡が入り、「お子さんが友達をケガさせたようです」と知らされました。
その瞬間、頭が真っ白になり、どう反応していいかわからない方も多いのではないでしょうか。
しかし、まずやるべきは「何が起きたのか」を冷静に把握することです。
子ども本人からの話はあいまいなことも多く、感情的に問い詰めても正確な情報は出てきません。
先生や第三者(目撃者)からの話も合わせて、複数の視点で状況を整理することが大切です。
②学校との連携:担任と密にやり取りする姿勢が大切
今回のようなトラブルでは、担任の先生との連携が非常に重要になります。
先生も驚いていることが多く、すぐに正確な判断がつかない場合もあります。
そんなときこそ、親のこちらが冷静になり、
経緯を都度共有しながら協力的な姿勢を見せましょう。
「初めてのことでよくわからないのですが、どう対応したらいいですか?」という聞き方は、
先生にとっても好印象です。
学校と敵対せず、味方にする姿勢が円満解決への第一歩です。
味方は多いほうがいいです。
③謝罪の順序:相手方とどうコンタクトを取るか
謝罪は早ければ早いほど良い、というのが基本ですが、連絡の取り方には注意が必要です。
今回は先生を通じて相手の連絡先を教えてもらいましたが、
「先生経由で」だけで済ませてしまうと回りくどくなりがちです。
できれば、先生に「私の連絡先を相手の方にお伝えください」とお願いし、
相手から連絡をもらう形にするのがスマートです。
(電話が着たら取った後、すぐ折り返すことも忘れずに!小さなことですが相手の負担にならないようにしましょう)
また、電話に出られない場合はSMSなどで簡潔な謝罪と挨拶を送り、
誠意を伝える工夫も必要です。
連絡手段一つにも、相手への配慮が表れます。
親として“加害者対応”に必要だった5つのこと
①録音の重要性:自分と家族を守るために
今回のケースでは、相手が穏やかな方だったため問題は大きくならずにすみました。
しかし、万が一相手が感情的になったり、後から話が食い違ったりする可能性もあります。
そんなときのために、ボイスレコーダーなどで会話を記録しておくのは非常に有効です。
録音は「相手を疑う」ためではなく、「お互いを守る」ための手段です。
小型で操作が簡単なボイスレコーダーをひとつ常備しておくと安心です。
ボイスレコーダー #PR
②謝罪連絡の仕方:SMSと電話の文面と順番
連絡先がわかったあと、まずSMSで以下のような内容を送りました。
・今回の件の謝罪
・明日改めてお電話させていただく旨(※今回は時間が遅かったために別日程となった)
・電話可能な時間の確認
こうすることで、いきなり電話をかけるよりも相手に配慮を示せます。
翌日、指定の時間に電話し、
丁寧に謝罪と経緯のすり合わせを行いました。
③謝罪時の持ち物:手土産は必要?金額や選び方
今回のけがは軽傷と聞いておりました。手土産は必ず持参しましょう。
選んだのは家族で食べられるようにした2000円程度のお菓子です。
相手の家庭の家族構成も考慮し、個包装で人数分に対応できるものを選びました。
金額は、けがの程度や相手の対応によって調整してよいでしょう。
以下はあくまで目安ですが、手土産の相場の参考例です。
- 軽傷(擦り傷など):1000〜2000円程度
- 中程度(内出血や腫れがあったなど):2000〜3000円程度
- 病院通院あり:3000〜5000円+補足の菓子折り
「形」ではなく「気持ち」を示すアイテムとして考えると良いです。
外で会う場合には別れ際に渡すのがベストです。
のしは不要ですよ。
④子どもを連れていくべきか?教育的観点から考える
今回は放課後だったため、子どもを連れて謝罪に伺いました。
相手の親御さんも落ち着いており、冷静に話せる状況だったからこそ、子ども同席が可能でした。
しかし、もし相手が感情的であった場合、子どもを連れていくのは避けるべきだと思います。
事前に子どもには「なぜ謝るのか」「どんな言葉を使えばよいか」をシミュレーションしました。
本人が自分の言葉で謝罪する姿を見せることは、相手にも誠意が伝わります。
下の子がいたため連れて行かざるを得ませんでしたが、できれば預けた方が話し合いはスムーズです。
⑤学校への報告と相談:都度の共有がトラブル回避に
相手の親御さんとのやり取りや、家庭での指導内容は、逐一先生に電話と連絡帳で報告しました。
連絡帳は言った言わないの齟齬が出ないようにするため、電話では結果と簡単な経緯を報告としました。
先生も「今後の指導に役立てたい」とのことで、とても丁寧に対応してくださいました。
何か問題が起きたとき、「学校も知っている」という状況を作っておくと安心です。
また、先生の経験や判断を仰ぐことで、より冷静な対応ができるようになります。
「困ったときは助けてください」という姿勢が信頼関係を築きます。
先生や学校も大小様々なトラブル対応(親対応も含め)に馴れているはずなので、
先生に積極的に相談しながら対応を進めましょう。
学校のせいにはせず、「子どもがしたことは親が責任を取る」とはっきり伝えています。
当然ですが、自分のこどもですからね。
親が心に留めたい“誠意”の伝え方
①「100%悪い」と断言しない誠実な伝え方
加害者側として「うちの子が悪いんです」と断言したくなる気持ちもわかります。
でも、子どもの前でそれを強く言いすぎると、子供が大きく傷つくことも。
「ケガをさせてしまったことに対しては本当に申し訳なく思っています」など、
事実と誠意を分けて伝える工夫が必要です。
謝罪は大切ですが、子どもを精神的に追い詰めない配慮も親の役目です。
バランスが難しいですが、「守りつつ、誠意を見せる」姿勢が大切です。
②謝罪の中で大切にした言葉の選び方
感情が高ぶると、つい強い言葉や余計なことを言ってしまいがちです。
「絶対にもうしません」「なんでそんなことを…」という言葉も時に誤解を生みます。
謝罪の際は、聞かれたことに対してだけ誠実に答えるのが基本です。
言い訳を避けつつも、こちらの考えやとらえ方を丁寧に伝えることも必要だと感じました。
たとえば、
「今回の件は大人が見ていない状況で起こってしまった」
「まだ子どもなので完全に制御することは難しい」という事実も共有しました。
「絶対にもう起こりません」とは言い切れないことも、誠実に説明しました。
できない約束はせず、「今後できる限り気を付けます」という伝え方を選びました。
このように、相手の受け取り方に配慮しながらも、自分たちの立場や思いを伝えるバランスが大切です。
③加害者の親として、子どもに背中を見せる
謝罪は親の責任ですが、それを見ている子どもにも多くの学びがあります。
今回は「お母さんが責任をもって対応するよ」と伝え、安心感を与えることを意識しました。
同時に、子ども自身にも「自分で謝る」経験をさせたことで、大きな成長につながったと感じます。
「親が逃げない姿勢」は、子どもの中にしっかりと残ります。
子どものミスを責めるより、「どう立て直すか」を見せる姿勢が大切です。
親が攻め立てて逃げてしまうとそれが悪い見本になってしまい
子どもも必ず真似をします。
夫とも相談しながら、逃げずに誠意を尽くすことを必ず見せてください。初動が大切です。
万が一に備える防衛策:ボイスレコーダーと保険の話
①おすすめのボイスレコーダーはこれ!楽天で買える
学校や相手家庭との話し合いで役立つのが、ボイスレコーダーです。
スマホでも録音できますが、通知音やバッテリー切れの心配があります。
おすすめは、ワンタッチで録音できて、USBでPCにも簡単に移せるタイプ。
楽天では、3000〜5000円程度で高性能なモデルが手に入ります。
いざというときの備えとして、親の必須アイテムになりつつあります。
ボイスレコーダー #PR
|
|
②子どものトラブルに備える保険:FP相談という選択肢
万が一、相手に治療費や慰謝料が発生した場合、家計の負担は小さくありません。
そんなときに備えておきたいのが、「個人賠償責任保険」です。
自転車保険や火災保険に付帯できることもあり、知らないと損をします。
どの保険にどんな補償がついているかを無料で相談できるFPサービスを活用するのがおすすめです。
家庭に合った保障をプロに見直してもらい、安心感を手に入れましょう。
PR
今回は、子どもが学校で友達をケガさせてしまったというトラブルを通じて、加害者側の親としてどのように行動すべきかを振り返りました。
事実の把握、学校との連携、相手方への謝罪、そして家庭での指導まで、どのステップもひとつひとつが重要です。
また、録音機器の備えや保険の見直しといった“もしも”への備えも、改めて必要性を実感しました。
「絶対に起きない」ではなく、「起きたときどう動けるか」が親としての準備なのかもしれません。
この記事が、同じような経験をした方や、これから起こり得る事態に備える親御さんの支えになりますように。
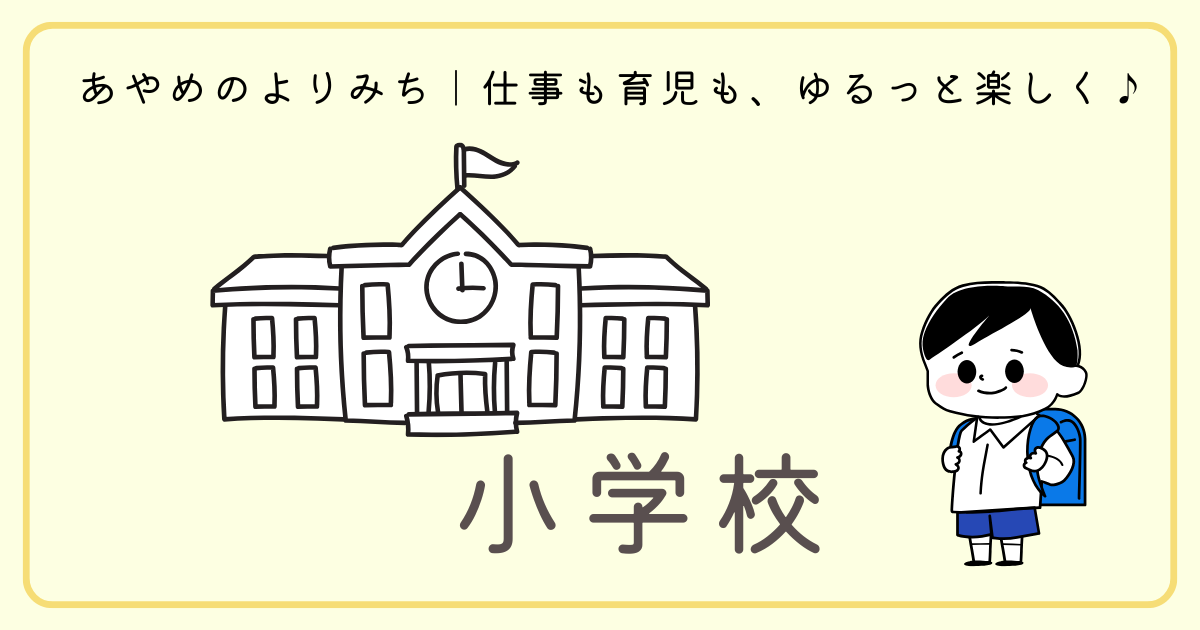

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cf9f6e8.09f40101.4cf9f6e9.254b53e6/?me_id=1405203&item_id=10004914&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fhiromifashionhouse%2Fcabinet%2F10166706%2F10796629%2Fimgrc0109647028.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

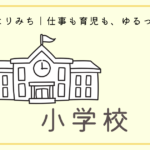
コメント