こんにちは、5歳差の子どもたちを育てているあやめです。
上の子の学校行事参加時の悩みは、同じ年齢差の兄弟姉妹を持つ保護者なら誰もが直面する問題ではないでしょうか。
今回は、特に緊張感の高い「入学式」に焦点を当て、下の子の対応策を徹底解説します。
入学式は人生の節目—下の子対応で失敗しないために
入学式は上の子にとって一生に一度の大切な日。
この特別な日を家族全員で心から祝福したいものですが、
下の子の存在が悩みのタネになることも。
事前の準備と適切な判断で、思い出に残る素敵な日にしましょう。
対応策その1:同伴の可能性を探る
✅ 学校への事前確認は必須
学校へ下の子の同伴可否を確認しましょう。
先輩ママさんに去年以前の状況を聞いたり、学校説明会などで先生に直接聞くと良いです。
学校によって方針が異なるため、自己判断は禁物です。
【同伴OKの場合の準備と注意点】
同伴が許可されても、他の家族の大切な時間を妨げないよう最大限の配慮が必要です。
事前準備リスト
- 静かに楽しめるおもちゃ:音が出ないもの、光るものなど(タブレットは要検討)
- 特別なおやつ:音が出にくく、手が汚れないもの(グミ、チーズなど)
- お気に入りの絵本:新しいものよりも既に夢中になっているもの
- 着替え一式:万が一に備えて
- 静かに遊べる工夫:シールブック、折り紙セットなど
当日の心構え
- 式場の後方または端の席を確保する
- すぐに退出できる位置を選ぶ
- 泣き出したらすぐに退出する覚悟を持つ
- 式の後半だけ参加するなど柔軟な対応も検討
周囲への配慮を忘れると、
「せっかくの式にずっと下の子が泣いていて集中できなかった」
「知らない子どもの鳴き声がビデオに写り続けて不快だった」といった感想を持たれかねません。
そうなると自分自身も落ち着いて式に参加できませんし、マークされるのも嫌ですよね。
対応策その2:信頼できる預け先を確保する
同伴NGの場合や、静かに過ごせる自信がない場合は、適切な預け先を探しましょう。

私は同伴OKでも預かりにしました。入学式自体をやり過ごせてもそのあとの教室で荷物が配られたり、学校によっては保護者会があるようで拘束時間が読めなかったから。
ぐずり始めたら止められないからね。
【預け先徹底比較】
同伴NGの場合や、静かに過ごせる自信がない場合は、適切な預け先を探しましょう。
ファミサポって実際どうなの?社会福祉士が内部事情まで徹底解説!【2025年保存版】
一時保育
- メリット:専門的な保育、施設が整っている
- デメリット:4月は新入園児対応で受入困難なケースが多い
- 費用目安:1日2,000〜3,000円程度
- 予約のコツ:入学式の2〜3ヶ月前から問い合わせを

4月は保育園も新入園児でてんやわんやの時期。一時保育の余裕がないケースが多く、私も2月時点で断られました。
2. ファミリーサポートセンター事業
- メリット:地域密着型、柔軟な対応が可能
- デメリット:提供会員の質にばらつきがある
- 費用目安:時給500円~800円前後(地域により異なる)
- 選び方のポイント:
- 保育経験者かどうか
- 自宅までの距離
- 預かり環境の安全性と清潔さ
- 同時に預かる子どもの人数

私が選んだ提供会員さんは:
元保育士で10年以上、
全年齢クラスの担任経験あり
自宅から徒歩10分以内の場所
提供会員宅が整理整頓され清潔(実際に訪問して確認済み)
同時に預かる子どもが2〜3人のみで目が行き届く環境
3. 民間ベビーシッターメリット:専門性が高い、マンツーマン対応
- デメリット:費用が高額
- 費用内訳(実例):
- 基本料金:時給1,700円×5時間=8,500円
- 交通費:往復1,000円
- 初回登録料:5,000円〜10,000円
- 合計:14,500円以上

4月は予約が取りにくく、コスト面でも負担が大きいため、定期的に利用するにはハードルが高いと感じました。
💡 我が家の選択基準と決め手
最終的にファミリーサポートセンターを選んだ理由:
- 子どもの性格との相性:大人数よりも少人数の環境の方が我が子には合っていると判断
- 費用対効果:質の高いケアを適正価格で受けられる
- 継続性:今後も定期的に利用できる関係性を築ける
- 安心感:保育のプロによる対応
大人数の中での保育も社会性を育てる上で重要ですが、
特に小さな子どもの場合は静かな環境でのケアが安心です。
年齢が2〜3歳になれば一時保育も積極的に検討していきたいと思います。
まとめ:失敗しない入学式対策チェックリスト
✅ 2〜3ヶ月前
- [ ] 学校への同伴可否確認(入学説明会や就学前検診などで要確認)
- [ ] 一時保育の予約開始
- [ ] ファミリーサポートへの登録(未登録の場合)
✅ 1ヶ月前
- [ ] 預け先の最終決定
- [ ] 必要書類の準備
- [ ] 下の子との信頼関係づくり(お試し預かり)
✅ 1週間前
- [ ] 預け先への持ち物準備
- [ ] 緊急連絡先リストの作成
- [ ] 当日のタイムスケジュール確認
✅ 当日
- [ ] 余裕を持った行動計画
- [ ] 子どもの体調最終確認
- [ ] 緊急時のバックアッププラン
おわりに:子育ては長い旅、焦らず一歩ずつ
5歳差の兄弟育児は予想以上の困難が伴いますが、一つずつ乗り越えていくことで家族の絆は深まります。
入学式という特別な日に、上の子も下の子も、そして親自身も笑顔で過ごせるよう、
事前の準備を大切にしましょう。
今回の経験から、ファミリーサポートセンターとの良好な関係を築けたことは、
今後の子育てにおける大きな財産となりました。
皆さんも、地域の支援システムをぜひ積極的に活用してみてください。
きっと素敵な出会いがあることでしょう。
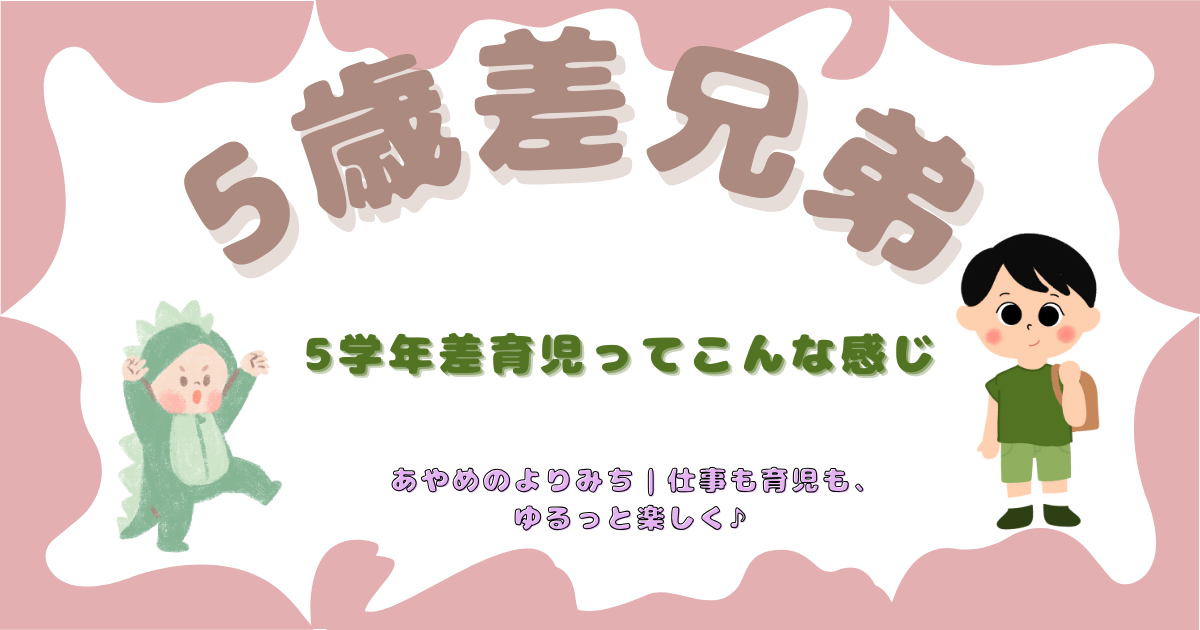

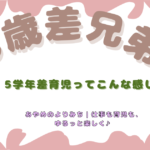
コメント