小学1年生の人間関係をうまくする5つのヒミツ
小学1年生にとって、「友だちと仲よくすること」は学校生活の中でとても大切なテーマですよね。
でも、どうやって仲よくなればいいのか、うまくできないときにどうすればいいのか、
悩んでいる子も多いと思います。
ここでは、小学1年生でもすぐにできる「人間関係をうまくする5つのヒミツ」を紹介します。
むずかしいことはなにもありません。
ちょっとした言葉や行動で、友だちとの関係がぐっとよくなるんですよ。
①あいさつを大切にする
人と仲よくなるために、一番かんたんで大切なのが「あいさつ」なんです。
朝、「おはよう!」と笑顔で言われたら、なんだかうれしい気持ちになりますよね。
「ありがとう!」や「バイバイ!」のような一言も、ちゃんと伝えるだけで、相手との距離がぐっとちぢまります。
たとえば、同じクラスの子に「おはよう」と言ってみたら、「おはよう!」って返してくれた。
それだけで、なんだかその子のことが少し近く感じたりしますよね。
あいさつは、魔法みたいなことば。
言うだけで、友だちができやすくなるんですよ。
②「なにしてるの?」と声をかける
だれかが遊んでいるとき、「なにしてるの?」って声をかけるだけで、そこから新しい関係がはじまることがよくあります。
友だちの輪に入るのって、ちょっとドキドキするかもしれません。
でも、思いきって「いれて~」や「なにしてるの?」と聞いてみると、案外「いいよ!」と返ってくるものです。
ある男の子が、ひとりで本を読んでいた子に「なに読んでるの?」と聞いてみたところ、
「これね、おばけの話!」と話がはずんで、一緒に図書室に行く仲になったということもありました。
声をかけるのって、勇気がいるけど、友だちを作る第一歩なんですよ。
③無理しないことも大事
人間関係って、うまくいくことばかりじゃないですよね。
ときには、「ちょっとこの子とは合わないな…」と思うこともあります。
そんなときに、無理に仲よくしようとしなくても大丈夫。
少しはなれて、自分の好きなことをしてみたり、一人でのんびりする時間もとっても大切です。
ある女の子は、おしゃべりがにがてで、にぎやかなグループにいるとつかれてしまうタイプでした。
だから、給食のあとには少し静かな場所で絵を描いたりして、落ちつく時間をもっていたんです。
それでも、クラスには「同じように静かな子」もいて、いつのまにか自然と仲よくなっていきました。
合わないときは、がんばらないでOKなんですよ。
④「ごめんね」と「ありがとう」は魔法のことば
ケンカをしたり、ちょっとイヤなことをしてしまったとき、「ごめんね」が言えると、また仲よくなれるチャンスになります。
逆に、なにかしてもらったときに「ありがとう」が言えると、「この子、いい子だな」と思ってもらえます。
「ごめんね」「ありがとう」は、すごくシンプルだけど、すごく大事なことばです。
ある日、おもちゃの取り合いでケンカになった男の子が、先生に「どうしたの?」と聞かれ、
「ぼくが先に使いたかったの。でも、先にさわったのは○○くんだったから、ごめんねって言ったんだ」と自分で気づいて謝ることができました。
そのあと、2人はなにもなかったようにまた遊んでいたそうです。
言葉には力があるんですよ。
⑤仲良しは1人でも大丈夫
「たくさん友だちがいないとダメかな?」って思うこと、あるかもしれません。
でも、本当に仲のいい友だちって、何人もいなくても大丈夫。
1人でも「わかってくれる子」がいれば、それはとってもすてきなことなんです。
何人かと遊ぶのが好きな子もいれば、1人か2人とゆっくり遊ぶのが好きな子もいます。
どちらもその子らしいやり方です。
「この子といると安心するな」って思える子がいれば、それだけでじゅうぶん。
大事なのは「自分らしいつながり」を見つけることなんです。
人間関係がうまくいかないときの対処法3つ
どんなにがんばっても、うまくいかないときってありますよね。
友だちとうまく話せなかったり、ちょっとイヤな気持ちになったり。
そんなときは、自分を責めるのではなく、ちょっと立ち止まって考えてみることが大切です。
ここでは、小学1年生でもできる「人間関係がうまくいかないときの対処法」を3つ紹介します。
①ひとりの時間をつくる
もし、「今日はなんか疲れたな」「友だちと話すのしんどいな」って思ったら、ひとりの時間をすごしてみましょう。
実は、人と関わることがつかれる日って、だれにでもあるんですよ。
そんなときは、ムリに話しかけたり、あそびに入ったりしなくても大丈夫。
図書室で本を読んだり、ベンチでおひるねしたり、好きなことをして心を落ちつけるだけでも、気持ちがスッと楽になります。
ある男の子は、休み時間になるといつもひとりで昆虫図鑑を見ていました。
でも、それを見た別の子が「ぼくも虫すきだよ!」って話しかけてくれて、自然と仲よくなったことも。
ひとりの時間も、自分にとって大切な時間なんです。
②大人に相談してみる
どうしてもつらくなったときは、自分だけでがまんしないで、大人に相談してみましょう。
先生やおうちの人は、あなたのことを見守ってくれているから、きっと話を聞いてくれます。
「こんなこと言ったら怒られるかな…」なんて心配しなくていいんですよ。
「今日○○くんにこんなこと言われたんだ」
「なんか最近、グループに入りづらいなあ」
そんな小さなモヤモヤでも、大人に話すだけで気持ちがスッと軽くなることがあります。
ある女の子が、クラスで「なんであそばないの?」と言われたことが気になって、先生に相談しました。
先生は「自分のペースでいいんだよ」とやさしく声をかけてくれて、その子は安心して過ごせるようになったそうです。
ひとりでかかえこまなくていいんですよ。
③場所や人を変えてみる
ずっと同じ場所や同じメンバーでいると、うまくいかないこともあります。
そんなときは、少しだけ「場所を変える」「話す人を変えてみる」ことで、気分がリセットされることも。
たとえば、教室の中でうまくいかなくても、図工の時間や体育の時間になると、ちがう友だちと仲よくなれることもあります。
休み時間にちがう遊びに入ってみるだけでも、新しい出会いがあるかもしれません。
ある子は、毎日一緒に遊んでいたグループとうまくいかなくなってから、昼休みに図書室に行くようになりました。
そこには本が好きな別の友だちがいて、今では「本の話をする親友」になっているそうです。
ちょっと動くだけで、関係が変わることってあるんですよ。
親や先生が子どもに伝えたいサポートのコツ
小学1年生は、まだまだ人との関わり方を学んでいる途中です。
うまくいくこともあれば、つまずくこともたくさん。
そんな子どもたちを見守る大人の役目は、「どうすればいいか教えること」よりも、「その子の気持ちに寄りそうこと」。
ここでは、親や先生が子どもにできるサポートのコツを紹介します。
①子どもの気持ちを聞く
いちばん大切なのは、子ども自身の「気持ち」に耳をかたむけることです。
「今日はどうだった?」「なんかあったの?」と聞くよりも、子どもが話し始めるまで、ゆっくり待つ姿勢が大事なんですよね。
大人が先に答えを出してしまうと、子どもは「言ってもムダかも」と感じてしまいます。
でも、ただ黙って「うんうん」と聞いてくれるだけで、「話してよかった」と感じる子が多いんです。
たとえば、ある男の子が「学校でだれとも話せなかった」とつぶやいたとき、お母さんが「そっか、それはさみしかったね」と言っただけで、ぽつぽつと話し始めたそうです。
まずは、「聞いてもらえた」という安心感が、心の支えになるんです。
②「がんばらなくていいよ」と伝える
子どもって、「友だちを作らなきゃ」「みんなと仲よくしなきゃ」と、知らず知らずのうちにプレッシャーを感じてしまうものなんですよね。
そんなとき、「無理しなくていいよ」「自分のペースでいいんだよ」と伝えてあげるだけで、心がふっと軽くなります。
ある女の子は、「きょうも○○ちゃんに話しかけられなかった」としょんぼり帰ってきたとき、
お父さんが「話しかけようって思えただけですごいよ」と声をかけました。
その一言で、「また明日もがんばってみようかな」と思えたそうです。
がんばることをほめるのではなく、「そのままのあなたでいい」と伝えることが、いちばんの応援になるんです。
③小さな変化に気づく
子どもは、気づかないうちに成長しています。
だからこそ、大人はその「小さな変化」に気づいてあげることが、とても大切です。
「今日、いつもより元気がないな」
「きのう話してた子と遊んでるみたい」
そんなちょっとしたことに目をとめて、「どうだった?」「楽しかった?」と聞いてみると、子どもは「見てくれてるんだ」と感じて安心します。
ある先生は、教室でぽつんと座っている子に「きょうはゆっくりしたい気分?」と声をかけました。
その子はうなずいて、それだけで少し笑顔になったそうです。
毎日の中で、ちょっとした変化に気づくことが、子どもの安心につながるんですよ。
自分らしい関わり方を見つけよう
「みんなと同じようにしなきゃいけない」って思っていませんか?
でも、ほんとうは自分らしい関わり方がいちばんなんです。
だれと、どんなふうに過ごしたいかは、人によってちがっていて当たり前。
ここでは、自分らしく人とつながるヒントを紹介します。
①無理に仲良くしなくていい
「みんなと仲良くしなきゃ!」とがんばりすぎると、心がつかれちゃうこともありますよね。
実は、「気が合わないな」「なんとなく合わないな」って感じることは、ぜんぜん悪いことじゃありません。
たとえば、おしゃべりが好きな子と、静かに絵をかくのが好きな子。
どちらかががまんして付き合っていたら、しんどくなってしまいますよね。
だから、「この子とはちょっと距離をとってもいいかな」って思ったら、それでOK。
仲良くできない日があっても、気にしないでくださいね。
人との関係は、自分の心が元気でいることがいちばん大事なんですよ。
②好きなことを通じて仲間ができる
無理に「友だちを作らなきゃ」と思わなくても、「好きなこと」をしていたら、自然と仲間が見つかることが多いんです。
好きな本、好きな遊び、好きな色、なんでもいいんです。
その「好き」を大事にしていると、「あ、それ私も好き!」って思ってくれる子が現れます。
ある男の子は、給食のあとに折り紙をしていて、それを見た子が「すごいね!おしえて!」と声をかけてきました。
それがきっかけで、いつのまにか折り紙仲間がふえていったそうです。
自分の「好き」を大事にしていると、自然に人があつまってくるんですよ。
③ちがってもいいんだと知る
「みんなとちがうのはダメかな?」って思うこと、ありませんか?
でも、ちがいがあるからこそ、世界はたのしいんです。
話すのがすきな子、聞くのがすきな子。
にぎやかな場所が好きな子、静かな場所が落ちつく子。
どっちが正しいってことはないんです。
ある女の子は、おしゃべりがにがてで、グループの中であまり話さなかったけど、ちがう子が「〇〇ちゃんが静かに笑うの、なんか好き」って言ってくれたことがあったそうです。
その一言で、「そのままでいいんだ」と思えて、自信がもてたそうですよ。
ちがいを受け入れることで、やさしい世界がひろがるんです。
「気持ちを伝える力」は練習できる!
ここまで読んで、「あいさつ」や「ごめんね」「ありがとう」の大切さを感じていただけたと思います。
でも、実はその“ことば”をうまく使えるようになるには、語彙力や**伝え方のコツ(SST:ソーシャルスキルトレーニング)**がとても大切なんです。
たとえば、「いやな気持ち」を伝えるにも、
「ムカついた」「いやだった」「かなしかった」「さみしかった」など、気持ちの言葉を知っていると、自分でも気持ちを整理しやすくなるんですよね。
そして、「どう伝えたら相手がわかってくれるか?」という“練習”も必要です。
これは「才能」ではなく「トレーニング」で育てていける力なんです。
語彙力やSSTをやさしく育てるのにおすすめの本
語彙力とSSTで「伝える力」を育てよう
気持ちを伝えることって、ほんとうはとてもむずかしいことです。
だからこそ、「うまく言えない」「なんて言えばいいのかわからない」そんな場面が、小学1年生にはたくさんあります。
でも大丈夫。
ことばの数がふえると、気持ちもじょうずに伝えられるようになります。
そして、それをどう伝えるかの「人とのやりとり」も、練習次第でどんどん上手になります。
そんな力を育てるのにぴったりの本を2冊、ご紹介します。
こども語彙力えほん きもちのことば
「うれしい」「くやしい」「さみしい」など、子どもの心にある“気持ちのことば”をイラストつきでやさしく紹介。
親子で読みながら、「こんなときどう感じた?」を話すきっかけにもなる一冊です。
「ちゃんと話せない」「うまく説明できない」と感じているお子さんにぴったりですよ。
小学生のためのソーシャルスキル・トレーニング
友だちとのトラブル、ことばの使い方、SNS時代のつきあい方…。
今の小学生に必要な「人間関係の技術」が、この1冊にぎゅっと詰まっています。
マンガ形式やイラスト解説も豊富で、親御さんにとっても読みやすく、家庭で使える実践本です。
どちらも「ことばを知る」「相手を思いやる」「気持ちを伝える」ための力を伸ばしてくれる内容です。
お子さんの人間関係に悩んでいる方や、今のうちにコミュニケーション力を育てたいという方には、ぜひ手に取っていただきたい良書です。
まとめ
小学1年生にとって「友だちとうまくやる」ことは、とても大きなテーマです。
この記事では、小学1年生 人間関係 ヒミツとして、子どもがすぐに実践できる5つのコツを紹介しました。
あいさつを忘れない、声をかけてみる、無理をしない、「ごめんね」「ありがとう」の魔法を使う、そして仲良しが一人でもいればいい。
そんな小さなヒントが、子どもの毎日をやさしく包みます。
また、人間関係がうまくいかないときの対処法や、大人ができるサポートの工夫、自分らしく関われる考え方にも触れました。
子どもも大人も、「うまくやらなきゃ」じゃなく、「自分らしくていい」と思えることが、いちばん大切なんだと感じていただけたらうれしいです。

![こども語彙力えほん きもちのことば [ 渡辺 弥生 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4609/9784816374609.jpg?_ex=128x128)
![小学生のためのソーシャルスキル・トレーニング スマホ時代に必要な人間関係の技術 [ 渡辺弥生 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7232/9784182237232.jpg?_ex=128x128)
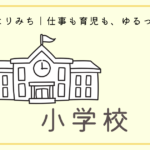
コメント