もうすぐ(あるいは、もう始まっている)小学校生活!
楽しみな気持ちと同じくらい、親としては初めての登下校、心配も尽きませんよね。
「ちゃんと一人で歩けるかな?」
「交通ルール、守れるかな?」
「もし危ない目に遭ったら…?」
そんな不安を抱えるママ・パパも多いのではないでしょうか。
実は先日、我が家の小1息子がまさに登下校中に帽子を飛ばしてしまったのですが、「ママとの約束だから」と帽子を追いかけずに帰ってくるという出来事がありました。
(このエピソード、SNSで予想以上の反響をいただきました…!)
Threadsで見る
多くの方から「うちの子も心配」「大事な視点ですね」という声をいただき、改めて考えたんです。
(本当にThreadsの皆さん優しくて感謝です…!)
なぜ息子は、とっさの場面で約束を守れたのだろう?と。
もちろん、まだまだ未熟な息子ですが、もしかしたら、
入学前に行った「ただ付き添うだけじゃない、ちょっとした工夫を取り入れた登下校練習」が、少しでも役に立ったのかもしれません。
そこでこの記事では、
「ただ小学校に行って帰るだけでは効果が薄いかも?」
と感じている方に向けて、心理学的なアプローチも踏まえながら、
-
子どもの安全意識と自信を育む、効果的な登下校練習の5つの方法
-
練習中に親が気を付けたいポイント
-
登下校が楽しみになるような声かけのヒント
をご紹介します。
Ver2へ改変しました。
今からでも遅くありません! 不安な登下校を、親子の「できた!」と笑顔に変えるためのヒントが、きっと見つかるはずです。
小さな成功体験を積み上げよう(自己効力感)
親から離れて小学校に通う、それだけで子どもはどきどきします。
一人でできるかな、友達と一緒に行けるかな・・・。
登下校練習を積み重ねることで「自分はできる!」と自信を持つことが大切。
心理学の用語では「自己効力感(有力感)(Self Efficacy)」といいます。
自己効力感が高いと、新しい環境でも不安が少なく、自信を持って行動できます。
🔹やり方
- 段階的に成功体験を積む(出来ることから1つずつ)
-
最初は親と一緒に歩く
-
次に少し先を歩く(親は後ろから見守り)
-
徐々に一人で歩く距離を伸ばす
-
- 「できた!」の認識を大切にする(気付きを与える)
-
「信号でちゃんと止まれたね!」と小さな成功を言葉にする
-
「昨日よりスムーズに歩けたね!」と成長を実感させます
- 「最後まで歩けて学校に行けたね」と声にだします。
-
行動の習慣化
行動の習慣化
→ 安全な動きを、考えなくても自然にできるようにすること!
人は繰り返し行うことで、無意識に行動できるようになります。
登下校での安全行動も「習慣化」が鍵!自然と体が動くようになれば、いざという時も安心ですよね。
🔹ポイント
-
行動の準備には「トリガー」が大切
例)「横断歩道の前では必ず左右確認」→ 「白い線を見たら止まる!」とルール化する
-
「安全ポイント」を目印にする
「気にする」ことで行動を習慣にする(ナッジ理論)
ナッジ(nudge)理論とは、人がより良い選択を自発的に取れるように、そっと後押しするアプローチのこと。
例)「この信号を渡ったらポストの前で一度立ち止まる」など、決めた場所で行動を習慣化
-
親が見本を見せる(モデリング効果)
子どもは親の行動を見て学びます。これをモデリング効果と言います。
例)親が率先して「信号で止まる」「左右確認」を徹底する
「危ないからやめなさい!」ではなく、親が見本を見せる
- 登下校のルールを最初に決める(アンカリング効果)
例)毎回登下校前に「今日の安全ポイント」を確認
「最初に学んだことが強い印象に残り、その後の行動に影響を与える」という心理学の法則です。
思考の習慣化(認知負荷)
思考の習慣化(認知負荷)
→ 考えることをシンプルにして、行動に集中させること!
心理学には「認知負荷(Cognitive Load)」という考え方があります。
これは、「人が一度に処理できる情報量には限界がある」ということです。
登下校中、子どもは周りの景色、友達とのこと、天気など、たくさんの情報を処理しています。
そこに複雑なルールをたくさん詰め込もうとすると、
脳がパンクしてしまい(認知負荷が高くなり)、
かえって注意力が散漫になることも。
だから、安全ルールはできるだけシンプルにするのが効果的なんです。
やり方
-
「3つの安全ルール」に注目(シンプルな行動にする)
例:「信号を見る・周りをよく見て歩く・危ないと思ったら止まる」だけを徹底的に -
決めた時間に出発し、同じルートを通る
→毎日同じ動作を繰り返すことで、余計なことを考えずに(認知負荷を減らし)、安全な行動が取れるようになる
登下校へのわくわくを増やす
登下校へのわくわくを増やす
→ ネガティブな見方を、ポジティブな見方に変えること!
心理学には「リフレーミング」というテクニックがあります。
これは、物事の「枠組み(フレーム)」を変えて、違う視点から見ることで、前向きな気持ちになるという考え方です。
「雨の日の登校=大変」というネガティブなフレームを、
「雨の日の登校=冒険!」というポジティブなフレームに変えてあげるイメージですね。
やり方
-
「雨の日の登校=大変」ではなく「冒険」に変える
→ 「今日は水たまり探検の日!長靴でザブザブできるね!」とゲーム感覚にする -
「坂道がしんどい」ではなく「足が強くなる道」に変える
→ 「この坂を登ると足がもっと早くなるね!ヒーローみたい!」
また、行動心理学では、「楽しいこと」と結びつけると新しい習慣が定着しやすいと言われています。
「登校=ワクワクするもの」というポジティブなイメージを持つことで、
毎日の通学がスムーズになり、行きしぶりを防ぐ効果も期待できます。
登下校の楽しみを作る
-
「学校までの道に黄色い花をいくつ見つけられるかな?」とゲームにする
-
「学校に着いたら楽しみなこと(好きな先生に会える・今日の給食のメニューなど)」を話す
-
仲良しのお友達と登下校できるように約束する
🔹 「怖い」「不安」を考えてみる
-
お守りを持てる
例)親からのメッセージ入りお守りなど
-
朝のおまじないを作る!
例)「いってらっしゃい!」のハイタッチ
不安を減らし危機対応力を育てる
不安を減らし危機対応力を育てる
→ 「もしも」を体験・想像して、対応力を身につけること!
「いつもと違うことが起きたとき」こそ、学びのチャンス!
心理学には
「予測誤差(Prediction Error)」という考え方があり、
これは「思っていたこと(予測)と違う現実(結果)に直面したとき、
人はそれを強く学習する」というものです。
いつも同じ道、同じ状況だけでなく、
あえて「いつもと違う」状況を練習に取り入れることで、
「もしも」の時に自分で考えて行動する力が育ちます。
また、
「もし〇〇になったらどう対処するか?」を親子で具体的にシミュレーションすることは、
認知行動療法の考え方にも通じます。
認知行動療法は、考え方(認知)や行動に働きかけて問題を解決していくアプローチです。
事前に対応策を考えておくことで、不安を減らし、実際に行動しやすくなります。
具体的なシミュレーション(親子で「もしも」を考えてみよう!)
事前に対応策を考えておくことで、子どもの不安を減らし、実際に行動しやすくなります。
いくつか例を挙げてみますね。
-
道に迷ったら?
→ 「近くのコンビニやお店、『こども110番の家』、交番など、大人のいる安全な場所に行って助けを求める」練習をする。 -
知らない人に声をかけられたら?
→ 「『用事があるので急いでます』と言ってすぐその場を離れる」
「しつこい場合は『助けて!』と大声を出す練習」「防犯ブザーを鳴らす練習」など。
→ 特に『お母さんが事故にあったから一緒に行こう』
『〇〇(子どもの名前)知ってるよ、送ってあげる』など、
子どもが信用してしまいそうな言葉で誘われた場合の断り方も具体的に練習しましょう。
「知らない人には絶対についていかない」を徹底します。
-
天候や季節に応じた注意点(これもシミュレーション!)
-
雨の日:
-
傘で前が見えなくならないように持つ練習。
-
傘を振り回さない、お友達とぶつからないように気をつける練習。
-
-
特に傘の先(骨の先端)は尖っていて危ないので、周りの人との距離を保って歩くことの大切さも教える。
-
-
-
マンホールや側溝のフタ、タイルの上など、滑りやすい場所を避けて歩く練習。
-
カッパを着た時の視界の悪さや、フードで周りの音が聞こえにくくなることも体験しておく。
-
-
風が強い日: 「帽子が飛ばされても絶対に追いかけない!」「傘は危ない場合もあることを教える(飛ばされたり、前が見えなくなったり)」「風でふらついて車道に出ないように気をつける」
-
すごく暑い日: 「登下校前に水分補給する習慣(最近は水筒持参OKの学校も増えているので、下校前に水筒の水を満タンにすることを教えておくのも◎)」「帽子を必ずかぶる」「日陰を選んで歩く練習」「もし気分が悪くなったら、安全な場所で休むか、近くの大人に助けを求める練習」
-
寒い日・暗くなるのが早い日: 「手袋やマフラーで動きにくくならないか確認」「路面が凍結しているかもしれない場所を注意して歩く練習」「明るい色の服や反射材を身につける大切さを教える」「暗い道はなるべく避ける、または大人と一緒などのルールを決める」
-
-
信号や横断歩道で
-
青信号がちかちか点滅していたら?→「絶対に走らない!次の青信号を安全に待つ」
-
横断歩道がない場所を渡りたくなったら?→「遠回りでも必ず横断歩道や歩道橋のある場所まで行く」
-
-
持ち物が道路に落ちたら?(帽子・ハンカチや手荷物、袋など)
-
もし、大事なものが道路や危ない場所に落ちたり、飛んで行ってしまったりしたら…
やることは、たった一つ!
『絶対に追いかけない! 道路には絶対に出ない!』
これが、一番大切な命を守るための約束です。 -
じゃあ、どうすればいいの?
-
すぐに安全な場所(歩道など)に移動する。
-
どこに落ちたか、場所をしっかり見て覚えておく。 (「あの電柱のそば」「横断歩道の向こう側」みたいに)
-
落ちたものには触らず、そのまま、まっすぐお家に帰る。
-
お家に帰ったら、すぐに大人(ママやパパなど)に知らせる。 その時、「どこに落ちたか」覚えている場所を伝える。
-
-
なぜ自分で拾いに行ってはいけないの?
→ 道路は車がたくさん通っていて、とっても危ないから。ボールや帽子よりも、あなたの命の方がずっとずっと大切だからです。物はまた買えるけど、命は一つしかないからね。 -
この「追いかけないで、帰って知らせる」という約束を、親子でしっかり確認し、徹底しましょう。 (先日、うちの息子もこの約束を守って無事に帰ってきてくれました!)
-
-
もしものトラブル
-
急にお腹が痛くなったり、トイレに行きたくなったら? → 「安全な場所(お店や公共施設、知っている家など)をいくつか事前に確認しておき、助けを求める練習」
-
転んでケガをしてしまったら? → 「軽いケガならどうするか(ハンカチで押さえる等)、ひどいケガならどうやって助けを求めるか(近くの大人に助けを求める、家が近ければ帰る等)」
-
-
【集団登下校の場合】
-
もし集合時間に遅れそうになったら? → (家のルールを決めておく:例「〇分まで待っても来なかったら先に行っていいよ、と班長さんに伝えておく」など)
-
もし集合場所に誰もいなかったら? → (家のルールを決めておく:例「少し待っても来なかったら家に戻る」「近くの〇〇さんに声をかける」など)
-
もし班長さんや他の子がいつもと違う危ない道に行こうとしたら? → 「『そっちは危ないから行かないよ』と言う勇気」「一人でも安全な道を行く判断」などを話し合う。
-
途中で気分が悪くなった子がいたら? → 「周りの大人に知らせる」「班長さんに伝える」など、自分だけで解決しようとしないことを教える。
-
「もしもゲーム」で考えさせる
ただ教えるだけでなく、「〇〇だったら、あなたはどうする?」とクイズ形式で質問してみるのも効果的です。子どもが自分で考えるきっかけになります。
-
「雨の日に傘をさして歩くときに気をつけることは、あと3つあるかな?」
-
「下校中にお友達が転んじゃったらどうする?」
-
「知らない人に『お母さんが事故にあったから一緒に行こう』って言われたらどうする?」
-
「帰り道に急にお腹が痛くなったら、どうするんだったっけ?」
#PR
ただ、我が家では、次に買うならこちらを検討中です。(発売が2025年6月頃予定なので入学には間に合いませんでしたが…)
最初は親が付き添いますし、普段は友達と集団下校の約束なので、焦らず良いものを選びたいなと。
コクヨ『はろここトーク』
#PR
決め手は、子ども自身も使うことを考えた「直感的に分かりやすそうな操作性」です。
ボタンがシンプルだったり、音声でのやり取りが簡単そうだったりする点が魅力的に感じています。(あくまで現時点での情報ですが!)
GPSは機種によって機能や月額料金も様々なので、
ご家庭の状況や使い方に合わせて比較検討してみてくださいね。
【補助的な使い方として…エアタグも】
もっと手軽なものとして、Appleのエアタグをランドセルに入れておく、という方法もあります。
#PR
こちらはGPS専用機と比べると、
メリット:
-
比較的安価
-
月額料金がかからない
-
小さくて軽い
- iPhoneユーザーなら探しやすい
デメリット(注意点):
-
近くにAppleデバイスがないと正確な位置情報が更新されにくい
-
音声通話などの機能はない
-
子どもが使うものなので、紛失や破損の可能性も(我が家は念のため2個入りを買って1つは予備にする予定です…😅)
という特徴があります。あくまで「補助的な見守り」や「紛失防止タグ」としての活用が良いかもしれません。
今後の追加予定
・親同士の信頼がカギ!(親⇔親)小学生の“もしも”に備える|遊びトラブルを防ぐ7つの約束+α
・親子でできる体と心の体調管理
・学校生活のルールと先生との付き合い方
を更新予定です。お楽しみに!
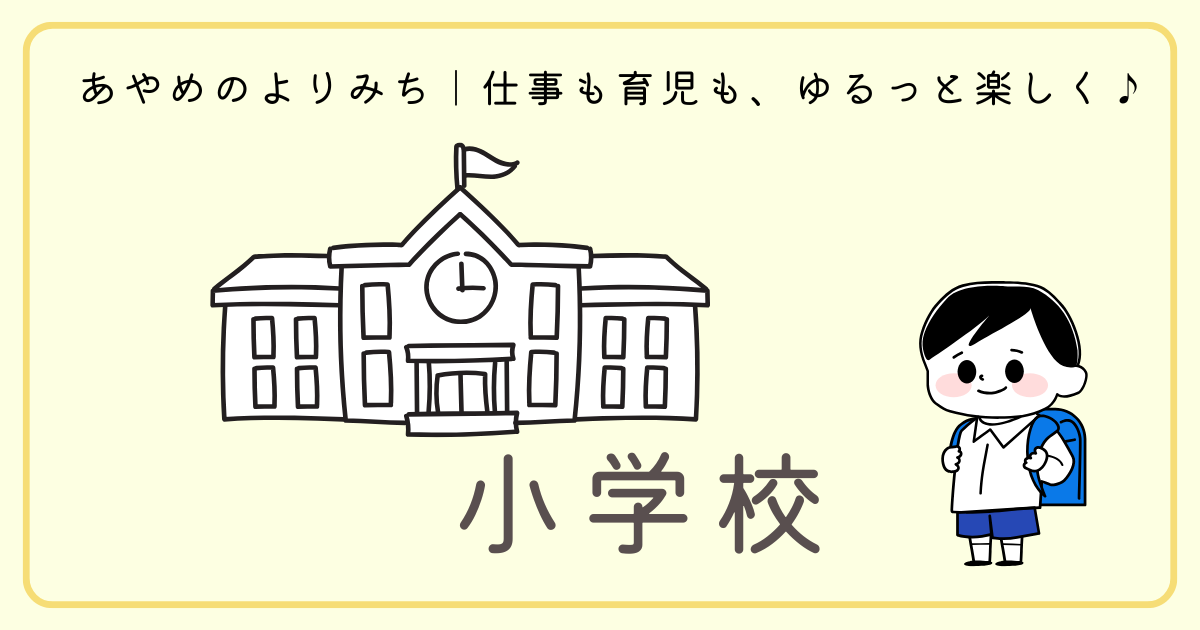


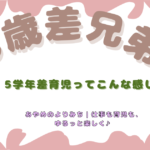

コメント